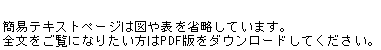
| 全文(PDFファイル:125KB、2ページ) |
| 機能性非衣料繊維の開発 ―感温色素剤を練り込んだ繊維の開発と応用― |
||
| ■繊維生活部 〇木水貢 山本孝 杉浦由季恵 森大介 守田啓輔 ■ウーブンナック(株) 西弘三 |
1.目 的
1990年代後半から,繊維産業は中国,台湾,韓国等のアジア諸国の台頭によりその合成繊維の生産シェアが大きく変化している。そのため,日本の繊維産業の繊維製品生産量が減少し,21世紀に入り,これまで築き上げてきたシステムが機能しなくなってきた。日本の繊維産業は川上である紡糸メーカを中心とし,川中,川下の生産工程を一貫した系列形態を形成し,繊維の素材力と企画によって生産が決定されていた。しかし,上記のアジア諸国の席巻で,合繊メーカの紡糸生産量が減少し,縮小や撤退を余儀なくされている。その影響で,系列形態は解消され,これまで系列により委託されていた生産量を独自で確保しなければならなくなり,そのため,北陸産地の中小企業においても,企画力強化が必要となっている。このため,工試では県内企業の企画力向上のため,これまで行われてこなかった繊維素材からの提案を可能にする機器である樹脂溶融混練装置やマルチフィラメント製造装置(図1)等の設備導入を行い,開放している。
本研究では,機能性繊維の開発で,繊維内に機能剤を練り込んで繊維を紡糸する技術を検討した。特に,機能剤として温度によって色を変化させる色素剤を練り込んだ繊維の開発を行った。
(図1 マルチフィラメント製造装置 )
2.内 容
2.1 感温色素剤
図2に示すように複素環を持つ色素剤の中には,酸によって色素剤の環が開環し,発色作用を示す色素剤がある。この開環・閉環に伴う着色−消色の化学的反応は可逆的なものであり,この作用を引き起こすことで特定温度領域において着色・消色を示す感温色素剤を用いた。
(図2 感温色素剤の一種 )
2.2 紡糸条件
非衣料に多く使用されている繊維のポリプロピレン繊維は,強く,軽く,そして化学的安定性など多くの利点を持つが,染色性が極端に悪い。そのため,その利用用途は限られ,着色も原着のみで行われてきた。本研究では,幅広いポリプロピレン繊維の利用を目的とし,このポリプロピレンをベースに上記の感温色素剤を練り込み,その紡糸条件について検討した。
2.3 耐光性試験
感温色素剤は紫外線に弱いため,その耐性は著しく悪い。そのため,今回は紫外線吸収剤を紡糸段階で感温色素剤と同時に練り込み,繊維化を行った。その耐光性評価については,カーボンフェードメータと色差計を用いて検討した。
3.結 果
3.1 紡糸試験
色素である染料は高温で昇華してしまうため,練り込み・紡糸での成形温度を210℃以下としなければならない。また,感温色素剤はマイクロカプセルでできており,圧に弱く成形圧を高くすることができない。そのため,低温で流動性の良いグレードの樹脂材を選択することで,紡糸条件を見出すことができた。図3には,試作した繊維を示す。体温で色相が変化することが確認された。
(図3 感温繊維(手の温度で変化する) )
3.2 耐光性試験
感温色素剤の耐光性を向上させるため,数種類の紫外線吸収剤について検討したところ(表1),ブルースケール3級以上の耐光性を示すことが分かった。さらに,耐光性を向上させるため,コーティングで紫外線吸収剤を塗布したところ,耐光性が更に向上することが確認された。
(表1 各感温色素における耐光試験結果 )
試料 色差ΔE 試料 色差ΔE
ブルースケール 10.92
P-紫外無 30.02 P-紫外有 5.72
TB-紫外無 27.43 TB-紫外有 5.24
GO-紫外無 29.61 GO-紫外有 3.91
*ブルースケールは3級での比較
3.3 感温繊維の用途展開
上記で確立した技術を用いて紡糸メーカにてマルチフィラメントの生産を委託し,その繊維を用いて撚糸,製織,後加工等の一連の試験を行い,その生産工程を確立した。製品としては,ジャガード織物,細巾ネーム,帽子,カバン等数点を試作した(図4)。
今後は,県内企業を中心に開発した繊維を利用した製品開発を提案し,商品化を行っていく予定である。
(図4 感温繊維を用いた試作品 )