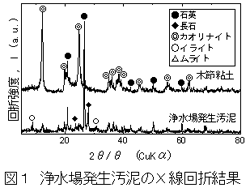
3.結果と考察
3.1 試料の物性
3.1.1 化学組成
表2に浄水場発生汚泥と木節粘土の化学組成を示す。 表から浄水場発生汚泥には,SiO2,Al2O3を主成分とし,木節粘土に比べIg.loss,アルカリ金属,アルカリ土類金属及び鉄の含有量が多いことが判る。
|
表2 化学組成 (wt%)
|
3.1.2 鉱物組成
図1は浄水場発生汚泥のX線回折パターンを示す。図から,浄水場発生汚泥は,石英,長石,イライト及びカオリナイトを主要鉱物としていること,イライト及びカオリナイトの回折値は,石英や長石に比べて小さいことが判る。この結果のみでは判断できないが,一般的な粘土と比較し明らかに可塑性を示す粘土鉱物(例えば,カオリナイト)の含有量が少ないので,浄水場発生汚泥は可塑性に乏しいものと推定できる。
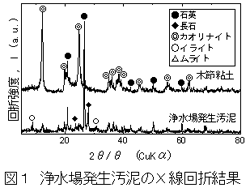
3.1.3 粒度分布
図2に試料の粒度分布測定結果を示す。図から,浄水場発生汚泥の粒径は1μm~20μmの範囲で,平均10μm程度であることが判る。一方,木節粘土は浄水場発生汚泥より微細であり,最小粒子径は0.07μmであることが判る。一般に,粘土類では可塑性は微細粒子の割合及び比表面積の大きさに影響を受けることから,木節粘土が浄水場発生汚泥に比べ優れた可塑性を示すことが推定できる。
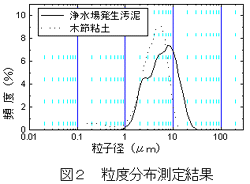
3.1.4 電子顕微鏡観察
図3に試料の電子顕微鏡観察結果を示す。図から浄水場発生汚泥は,1.0μm~2.5μmの板状粒子が凝集しているものであることが判る。この凝集は,ポリ塩化アルミニウムの凝集効果に起因しているものと考えられる。一方,木節粘土は,粒径が0.2μm~2.0μmの板状粒子からなり,0.3μm程度の六角板状結晶が数多く観察される。
一般に粘土類では,粒子が板状で微細であるほど高い可塑性を示すとされている。即ち,粒子間の接触面
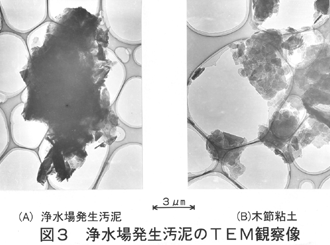
3.1.6 示差熱分析
試料の示差熱分析結果から,浄水場発生汚泥は45℃で吸熱ピークを示し,約340℃で発熱ピークを示すことが判った。45℃から110℃の吸熱は,粒子表面の吸着水,層間水及び自由水等の放出に寄与するものと考えられる。また,発熱は,有機物の燃焼によるものと考えられる。
3.1.7 比表面積
浄水場発生汚泥の比表面積は19.48m2/g,木節粘土は36.31m2/gであった。木節粘土は浄水場発生汚泥と比較し倍以上の比表面積を持つことが明らかとなった。
比表面積は粒子の分布状態やその形に寄与するものと考えられ,粒子が微細であればあるほど粒子間隙率は減少し,粒子間の凝集力も強くなり,可塑性の向上に寄与するとされている。従って,比表面積の小さい浄水場発生汚泥は可塑性に乏しく,比表面積の大きい木節粘土は優れた可塑性を示すことはこのことからも推定できる。
3.1.8 陽イオン交換容量
試料の陽イオン交換容量は,浄水場発生汚泥で10.52meq/100g,木節粘土で17.75meq/100gであった。陽イオン交換容量は,粘土鉱物に吸着する交換性陽イオンの量であり,その吸着陽イオン量から粘土鉱物の有無が判断できるとされており,木節粘土の陽イオン交換容量の値が大きいのは,カオリナイト等の粘土鉱物を多く含んでいることによる。
試料のpH値は,浄水場発生汚泥でpH値6.2~7の中性から弱酸性の範囲内にあった。木節粘土のpH値もほぼ同様な値であった。また,電気伝導度は,浄水場発生汚泥で240μS/cm,木節粘土で87.5μS/cmであった。電気伝導度は,アルカリ土類金属等の可溶性塩類の含有量により変化するものである。従って,木節粘土の電気伝導度が小さな値を示したのは,アルカリ成分の含有量が少ないことによるもので,化学分析結果と矛盾はない。
3.2 可塑性試験
3.2.1 練土の熟成効果
図4は,成形助剤の添加量が異なる浄水場発生汚泥について,熟成時間によるpH値の変化を示したものである。図から,熟成により酸性化すること,熟成時間200時間で一定となることが判る。また,添加量により,pH値の変化の傾向が異なり,pH値の変化度合いはは,成形助剤の添加量とともに増加している。従って,糖を主成分とする成形助剤が有機酸に変化したものと指定される。
従って,成形助剤が分解され浄水場発生汚泥と均一な混合物を形成するのは,200時間程度の熟成時間が必要であることが判る。
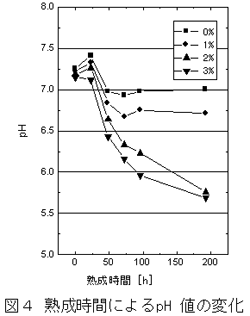
3.2.2 Pfefferkorn法
図5には,浄水場発生汚泥の含水率を変化させた時のPfefferkorn法における変形比の変化を示したものである。図から,各乾燥温度により見掛けの含水率は変化するが,乾燥温度に依らず変形比と含水率は同様な傾向を示すことが判る。
表3には,図5から求まる両者の相関係数を示す。さらに,表4には成型助剤添加による可塑特性値等の変化を示す。
表3より Pfefferkorn試験法では,含水率と変形比については高い相関性を示すことが判る。
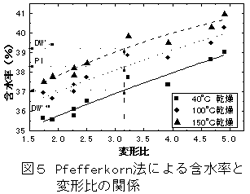
| 添加量 | 式(X=変形比,Y=含水率) |
| 相関係数(r) | |
| 0% | Y=32.434+2.7687X-0.2476X2 |
| r=0.9560 | |
| 1% | Y=33.660+1.9163X-0.1263X2 |
| r=0.9761 | |
| 2% | Y=30.507+4.9614X-0.5462X2 |
| r=0.9977 | |
| 3% | Y=33.317+3.8077X-0.4222X2 |
| r=0.9840 | |
| 木節粘土 | Y=28.088+2.5263X-0.1615X2 |
| r=0.9921 |
表4 Pfefferkorn法における成形助剤の添加量 による可塑特性値の変化
| 1% | 1% | 2% | 3% | 木節粘土 | |
| DW'40[%] | 36.75 | 37.80 | 38.93 | 39.99 | 33.37 |
| PI [%] | 37.75 | 38.98 | 40.20 | 41.27 | 34.67 |
| DW'150 [%} | 39.44 | 39.85 | 40.86 | 42.00 | 35.34 |
| WR100 [%] | 1.00 | 1.18 | 1.27 | 1.28 | 1.30 |
| WR150[%] | 2.99 | 2.05 | 1.93 | 2.01 | 1.97 |
| CV[%] | 2.65 | 3.03 | 3.16 | 3.10 | 3.76 |
| WPI[Å] | 311.46 | 328.09 | 345.26 | 360.91 | 146.12 |
| W40[Å] | 8.25 | 9.93 | 10.91 | 11.19 | 5.49 |
表4より成形助剤の増加に伴い浄水場発生汚泥は,各パラメータにおいて増加傾向を示した。しかし,CV値(可塑特性値)は,木節粘土に近づいていることから可塑性の向上していることが推定されるが,添加量による差は認められない。しかし,手による成形では,3%成形助剤を添加した浄水場発生汚泥では,明らかに1%添加のものより可塑性向上が認められた。従って,従来の可塑性の評価に用いられる可塑特性値(CV)では,成形助剤の添加効果が充分に評価することができないと考えられる。
3.2.3 一軸圧縮試験法
図6は,表1で示した条件で試験を行った時の荷重-変位の相関関係を示す。図における変形過程を初期,中期及び後期の3つに分類し,変位量が3mm程度までの初期変形過程より見掛け弾性率,変位量が8mm以降の後期変形過程より流動に要するエネルギーを求めた。
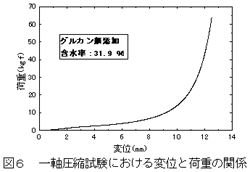 |
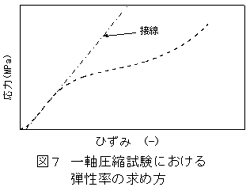 |
図7は,図6で示される初期変形過程を応力-ひずみの関係に変換して表したものである。図中の破線は初期の弾性変形領域を直線で近似しものであり,この直線の傾きを見掛弾性率とする。
図8は,一軸圧縮試験における変形後期過程での変曲点の求め方を示したものである。変形中期から後期の領域で荷重-変位の相関において各々接線を引き,この接線の交点での内角の二等分線とグラフの交点を変曲点とした。この点から終点(12.5mm)までを変形後期と定義とした。変形エネルギーは,この変曲点からの終点までの範囲を積分して求めた。変形エネルギーの値は流動に要した仕事量を意味し,流動性(成形性)と相関を持つものである。
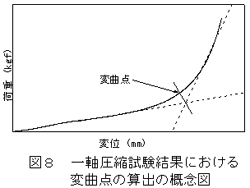
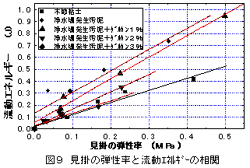
4.結 言
手取川水道事務所で発生する浄水場発生汚泥の有効利用を図るため,浄水場発生汚泥の化学組成・物性を調べ,可塑性の向上について検討した。また,可塑性の向上には成形助剤のβ-1,3-グルカンを用い,可塑性の評価は一軸圧縮試験法によった。
その結果,以下のことが明らかとなった。
| (1) | 浄水場発生汚泥には,アルカリ金属類の含有が木節粘土よりも多く含まれ,粘土鉱物としてイライトが含まれていた。 |
| (2) | 浄水場発生汚泥の平均粒子径は木節粘土と比較し大きな差異は認められなかったが,比表面積に関しては,木節粘土の方が倍以上大きな値を示した。 |
| (3) | 成形助剤であるβ-1,3-グルカンは,浄水場発生 汚泥の可塑性向上には有効であり,均質なものを 得るには,熟成に200時間程度必要であった。 |
| (4) | 一軸圧縮試験法で,浄水場発生汚泥に対する成形 助剤の添加効果を定量的に評価することができた。 特に3%添加したものは,木節粘土と同等な可塑性を示した。 |
謝 辞
本研究は,石川県企業局の受託研究として行われたものである。研究遂行に当たり資材等の提供を頂いた手取川水道事務所,金沢生コンクリート㈱,小松協栄瓦企業組合に感謝します。
参考文献
| 1) | 環境庁環境法令研究会編:環境六法平成5年度版, 東京,中央法規出版(1993)p885-875 |
| 2) | 中村静夫,渡部芳夫,山中一男,宮本正規,西村芳典:ク リーンジャパン,No.69,p.38-42(1988) |
| 3) | 阿久澤秀明,茂木敏彦,大野輝夫:埼玉県工業技術 研究所報告,Vol.3,p.52-61(1991) |
| 4) | 鍛冶茂樹,坂本忠士,武藤行弘:福岡県工業技術セン ター平成4年度業務報告,p.160(1992) |
| 5) | 志波雄三:佐賀県窯業技術センター平成6年度業務 報告書,p.62-66(1994) |
| 6) | 山本由忠:第32回全国水道研究発表会予稿集p.436-438(1981) |
| 7) | 辻口宏紀,津田隆成,佐々木喜一,萩原昇:第33回全国水 道研究発表会予稿集,p.211-213(1981) |
| 8) | 伴野巧,佐野三郎,小田喜一,芝崎靖雄:J. of Ceram.Soc. of J.,Vol.104,No.12,p.1147-1150(1996) |
| 9) | 芝崎靖雄:日本セラミックス協会東海支部学術研究発表会講 演予稿集,名古屋,日本セラミックス協会東海支部(1995)p.3-8 |
| 10) | 岩生周一,喜田大三,長沢敬之助,宇田川重和,加藤忠重, 青柳宏一,渡邉裕:粘土の辞典,東京,朝倉書店(1995) p.431-433 |
| 11) | 粘土学会編:粘土ハンドブック,東京,技報堂,(1967) p.29~40,p.131~135,p.413,p.485,p.854 |
|
|
|