3.1 漆塗膜の鉄含有量の違いと熱水による変色について
図2 鉄含有量と促進熱水試験による
色差の変化
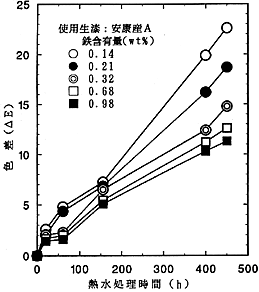 図2に鉄含有量と促進熱水試験による色差の変化を示す。
図2に鉄含有量と促進熱水試験による色差の変化を示す。
鉄の量を0.14〜0.98wt%に変化させて促進熱水試験を行った結果、鉄の添加量に関係なく、熱水処理時間の経過と共に色差は直線的に増加した。鉄の量が多くなると変色は少ないが、高粘度2)になり刷毛塗りが不可能となる。また、鉄着色だけでは変色を防止することはできない。しかし、変色をできるだけ少なくするには、刷毛塗り等を考慮し、鉄の添加量は0.3〜0.4wt%の量が適量であった。
3.2 なやし(攪拌)時間の違いと促進熱水試験による変色について
図3になやし時間の違いと促進熱水試験による光沢残存率を示す。
促進熱水処理時間が進むにつれて、光沢が減少することが分かった。特に、なやし時間0〜30分の短い塗膜は、熱水時間160時間後の光沢残存率が47.2〜54.3%と急激に艶を失った。また、なやし時間60分の塗膜は、長時間熱水にさらしても光沢の減少は緩やかで、160時間後では81.8%、480時間後では62.3%と光沢が保持できることが分かった。
図4に熱水浸漬試験前の塗膜の表面写真を示す。
図3 なやし時間の違いと促進熱水試験による光沢残存率
図4 なやし0分(NO.3)熱水浸漬試験前
光沢減少の原因は、図5、6が示すように熱水で塗膜表面が荒れたためと考えられる。特になやしをしない塗膜(図5)は、ゴム質が微細化していないため、穴が大きく表面が粗い。また、なやし時間の長い塗膜(図6)は、ゴム質の穴が小さく多数点在し荒れているように見えるが、同じ図11の表面は、平滑で緻密な状態が観察できる。これが熱水試験後でも光沢を保持できる要因と考えられる。
図5 なやし0分(NO.3)熱水浸漬試験80時間後
図6 なやし時間60分(NO.6)熱水浸漬試験80時間後
図7になやし時間の違いによる促進熱水試験後の塗膜の色差を示す。
なやし時間60分の塗膜は、促進熱水試験40時間後の色差が他の塗膜より小さく、初期の変色防止効果は期待できるが、熱水試験160時間後には、他の塗膜より色差が大きく長期間使用した場合、逆に変色度合いが大きくなることが分かった。
図8になやし時間の違いによる促進熱水試験後の塗膜の色味変化を示す。
なやし時間の違いによる色相(a* ,b*)は、促進熱水試験の時間経過とともに、黒から赤褐色や黄褐色に変化した。なやし時間0分の塗膜は、赤褐色であるが無彩色に近く、光沢が減少した分(光沢残存率が低い)短時間の熱水試験で白(L*値が大きい)く見えた。
図7 なやし時間と促進熱水試験による色差の変化
図8 なやし時間と促進熱水試験による色味の変化
また、なやし時間60分の塗膜の色相は、b*値が中心より大きく離れ、鮮やかな黄褐色に変色した。
図9は、熱水浸漬試験前の塗膜の断面写真であり、図10、11は熱水浸漬試験後の塗膜で、ゴム質が熱水により溶出し、空洞ができた様子が観察できる。これが褐色になる大きな原因であると考えられる。
特に図11は、なやし時間が長いため、ゴム質が微細化し塗膜内に多数分散されているので、小さな空洞部に光が当たるとより多く拡散反射を起こし、色相の変化が大きくなったと考えられる。
図9 なやし0分(NO.3)熱水浸漬試験前
図10 なやし0分(NO.3)熱水浸漬試験80時間後
図11 なやし時間60分(NO.6)熱水浸漬試験80時間後
3.3 つや剤の添加量と促進熱水試験による変色について
図12につや剤の添加量の違いによる促進熱水試験の光沢残存率を示す。
つや剤の添加量に関係なく熱水で徐々に塗膜の光沢が減少するが、つや剤10、15部添加の塗膜は、促進熱水試験500時間後の光沢残存率が82.8%、84.9%で、十分に光沢を保持する。しかし、つや剤0部、5部添加の塗膜は、促進熱水試験80時間後で、光沢残存率が84.5、84.4%で、短時間に光沢が減少した。また、つや剤20部添加塗膜は、促進熱水試験180時間後から急激に光沢が低下し、500時間後には、光沢残存率が67.5%とつや剤0部と同等の値を示した。従って、つや剤添加量の少ない塗膜や過剰な塗膜は、かえって光沢の減少を招くことが分かった。
図13につや剤の添加量の違いと促進熱水試験による色差変化を示す。
促進熱水試験の時間の経過と共に、徐々に色差値が大きくなり変色が進むが、つや剤10、15、20部添加の塗膜は、80時間まで色差ΔE7.0、4.4、4.6と小さく、つや剤の変色防止の効果が認められた。しかし、その後は急激に色差値が大きくなり、340時間後には、色差ΔE14.5、14.1、16.4で変色を防止する効果は無くなった。特につや剤20部は、500時間後で色差ΔE18.8の値を示し変色が一番大きくなった。
図14につや剤の添加量の違いによる促進熱水試験の塗膜の色味変化を示す。
つや剤の添加量の違いで促進熱水試験後の色味の変化が大きく異なることが分かった。
つや剤0部の塗膜は、黄褐色に色相が変化するが、長時間熱水(記号:E、F、G)にさらしても色相の変化は少ない。しかし、明度(L*)の値が熱水試験の初期(20時間)の段階で大きく変化し、早くから塗膜全体が白く見えた。
つや剤20部添加塗膜は、初期の段階での色相の変化は小さいが、180時間後(記号:E)から急激に黄味の強い褐色の色相に変化を起こした。また、明度は初期(80時間)の段階で効果があるが、長時間(340時間)熱水にさらされると急激に白くなることが分かった。
従って、つや剤の添加量については、一長一短あるが、塗膜が黄色に変化すると見た目に変色度合いが大きく感じるので、つや剤の添加量は少ない方が良い。
図12 つや剤の添加量の違いと促進熱水試験による光沢残存率
図13 つや剤の添加量の違いと促進熱水試験による色差の変化
図14 つや剤の添加量の違いと促進熱水試験による色味の変化