| 平成11年度研究報告 VOL.49 国際環境規格(ISO14001)の認証取得 |
| 製品科学部 | 奧野孝 漢野救泰 | 繊維部 | 沢野井康成 | |
| 管理部 | 竹中忠良 | 化学食品部 | 道畠俊英 | |
| 機械電子部 | 坂谷勝明 |
| 製品科学部 | 奥野孝 漢野救泰 | 機械電子部 | 西村芳典 | |
| 管理部 | 竹中忠良 | 繊維部 | 沢野井康成 | |
| 情報指導部 | 坂谷勝明 | 化学食品部 | 北川賀津一 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
平成10年度 国際環境規格(ISO14001)取得ワーキンググループ
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| The Authentication Acquisition of International Standard
for Environmental Management System (ISO14001) An international environment standard (ISO14001) acquisition working group 1998A.D. Takashi OKUNO , Tadayoshi TAKENAKA , Katsuaki SAKAYA ,Yasunari SAWANOI , Yasunari SAWANOI , Sukeyasu KANNO and Toshihide MICHIHATA 1999A.D. Takashi OKUNO , Tadayoshi TAKENAKA , Katsuaki SAKAYA , Yoshinori NISHIMURA , Yasunari SAWANOI , Sukeyasu KANNO and Kaduichi KITAGAWA |
| The IRII made an environmental policy , an environmental
management manual and a regulation in 1999.We acquired the authentication of the
international standard for environmental management system ISO14001 on February
23 , 2000 due to the following activities. In this paper , the acquisition progress
and the contents of execution are explained. (1) We make use of the photovoltanic power generating system and promote energy saving. (2) We collect the classified refuse and reduce the amount of paper for copy to make the effective use of the resources. And we carry out the development of technology about recycling and the environmental research. We are committed to the cause and use the know-how which got the authentication , and we support the enterprise. We regularly hold the meeting to evaluate the studies on environmental management system . (3) We reduce industrial wastes , specially controlled industrial wastes. Key Words:International Organization for Standarization, ISO14001, Environmental management system, Emvionmental Policy |
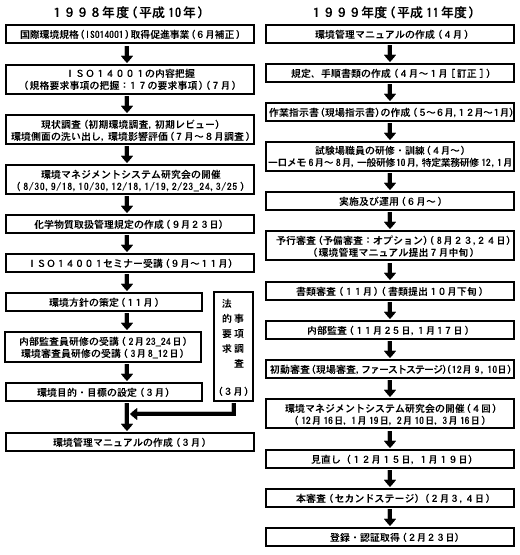 |
| 図1 国際環境規格(ISO14001)認証取得に向けた作業手順と実績 |
|
 |
 |
| 図3 環境マネジメントシステムの運用組織 | 図4 環境影響評価の適用範囲 |
| 3.3.1 環境側面 工業試験場は,県内産業支援のための指導相談・依頼試験・研究事業活動(図4)に関連する過去,現在及び今後計画するであろう事業の通常の実施状況や緊急事態等も考慮した環境側面の抽出,環境影響の評価を行い,著しい環境側面を管理対象として特定した(表1,2,3)。環境影響評価は、「環境影響評価表」を作成して行った。評価のための判断基準は、量・発生の可能性・影響の重大性を可能な限り定量評価するようにした。環境側面の継続的な見直しは年1回,更に見直しの必要が生じた時には,随時行い,環境側面を最新のものとしている。 当場では,電力,重油,プロパンガス,コピー用紙は一括管理しており,各部での使用量を把握できない。 特に,コピー用紙は全場一括購入でコピー室の棚に保管している。コピー機の紙がなくなれば棚から出して使用しており,プリンタに使う場合も,必要な職員が保管棚から自由に各部に持っていけるため,各部毎の使用量を出していない。そのため購入量とコピー機 のカウントにより,各部の使用量を案分,さらに各月の使用量も案分せざるを得なかった。 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
| 表4 法規概要登録表 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| 表5 目的及び目標 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| 表6 全場の環境マネジメントプログラムの概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 表7 全場環境マネジメントプログラム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境目的1:電力及び重油(ボイラ)の使用量を2001年度までに1998年度実績(143万kwh/年,142kL/年)を基準として,それぞれ2%(2.86万kwh,2.84kL)削減する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (責任者:技術次長) | ▽:確認時期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表8 全場環境マネジメントプログラム進捗状況確認表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境目的1:電力及び重油(ボイラ)の使用量を2001年度までに1998年度実績(143万kwh/年,142/年)を基準として,それぞれ2%(2.86万kwh,2.84kL)削減する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (責任者:技術次長) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年間教育計画は,場長の環境方針に従い全場的観点や各部門からのニーズを踏まえ,新採職員,一般職員,著しい環境影響を及ぼす作業(毒劇物等取扱い,特別管理産業廃棄物排出,危険物薬品使用等)に従事する職員,法規制に係わる業務,特殊な能力が必要な業務に従事する職員及び管理者,業務委託従事者,内部監査員毎に行った。 一般教育の例として,当場の全職員にISO14001の内容を周知させるため,事務局員が一口メモを作り,当場で運営している電子決裁システムを用いて,1999年(平成11年)6月から8月にかけて43回,全職員に回覧した。事務局員の意気込みが過ぎて,内容が難しく長くなったので,内容は少なく簡単にする方が回覧を見る職員も気楽に開くことができ,効果的だった。 特殊業務研修では,当場の専門職員が,騒音・振動,産業廃棄物の処理等についての特殊業務担当者を集め,研修を行った。 3.4.2 環境マネジメントシステム文書 環境マネジメントシステム文書とは,表9に示す第1レベルの文書である「環境管理マニュアル」で,それを補足する文書が第2レベル文書の「規定」,「基準」でその体系を表9の下部に示す。 3.4.3 運用管理 環境方針,目的及び目標に対する著しい環境側面に関連する運用及び活動を明確にし,大気汚染防止ではボイラーの排気,水質汚濁防止では実験廃水処理施設について法律の規制値より厳しい自主規制値を設け,管理を徹底した。廃棄物及び化学物質の管理でも定常時及び緊急時の対応を徹底した。省エネ・省資源では,昼時間の消灯,不用なOA機器の節電,冷暖房の温度管理及びコピー用紙の使用量の削減を図った。また,当場の特色である研究・指導に関してもリサイクル等の環境関連研究を年7テーマ,太陽光発電システムの普及等の指導を3テーマ以上を実施するように目的を設定した。さらに,供給者及び委託業務請負者に関連手順及び要求事項を伝達した。 |
 |
| 図5 燃料受入作業 |
 |
| 図6 ガス漏れ事故 |
|
|
|