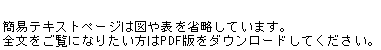
| 全文(PDFファイル:119KB、2ページ) |
| 無鉛和絵具の開発
|
||
| ■九谷焼技術センター ○木村裕之 |
1.目 的
九谷焼は石川県を代表する伝統産業の一つであり,高い透明感と独特の色調を持つ「九谷五彩」と呼ばれる色鮮やかな和絵具による装飾がその大きな特長として知られている。九谷焼に限らず陶磁器の上絵具には,その成分として鉛(酸化鉛)を含んでおり,鉛は酸性の水に触れると僅かながら溶け出すことが知られている。しかしながら,鉛は重金属であり,人体に影響を与える。このため,食品衛生法により「飲食器からの鉛溶出規格基準」が定められており,2000年に国際的な規格(ISO)の鉛溶出基準の改正(規制値が強化)が行われ,国内的にも食品衛生法の改正が予想されている。
鉛を陶磁器に使用する技術については,紀元前のメソポタミアやエジプト等での使用が確認されており,2000年以上の長い歴史を持っている。近年,環境や消費者の安全性に対する意識の向上のため,多くの分野で鉛を使用しないという動きがある。例えば,電子部品等の組み立てに使用するハンダにも鉛(金属鉛)が使用されている。しかし最近では鉛を全く含まないハンダが使用されており,無鉛ハンダ製品が製造されている。無鉛化は,時代のそして世界的な流れと言え,このような情勢から,石川県工業試験場では鉛成分を全く含まない和絵具の開発を行った。九谷焼独特の高い透明性と色調は鉛無しでは難しいと言われてきたが,従来の鉛を含んだ絵具に引けを取らない無鉛和絵具の開発を行った。
注:鉛溶出とは,4%酢酸溶液(食酢と同濃度)を食器に満たし,22±2℃の部屋の中に24時間静置することにより,酢酸溶液中に溶け出してくる鉛のこと。
2.内 容
陶磁器用上絵具は,それ自身は無色透明になるフリットと呼ばれる800℃前後で溶融するガラスに,色素である遷移金属元素等を混ぜて作る。この絵具のベースとなっているフリットの成分として,鉛が使用されている。特に,和絵具は高い透明性を持つために鉛を必要とし,鉛を含んでいることで,ガラスの屈折率が増加し,和絵具独特のキラキラした表面光沢が生み出される。また,鉛を含んでいることでガラスの融点が下がり,800℃前後での焼付けが可能になる。
2.1 無鉛「九谷五彩」の開発
まず,絵具のベースとなる鉛を含まないフリットを試作し,試作フリットについて九谷焼の和絵具に使用できるか検討を行った。
「九谷五彩」とは,九谷焼で使用する五色の色鮮やかな上絵具のことで,五色とは,赤,黄,青(緑),紺青,紫である。色素として,赤と黄は酸化鉄,青(緑)は酸化銅,紺青は酸化コバルト,紫は酸化マンガンを使用している。各酸化物を色素として無鉛フリットに使用し,無鉛和絵具を試作し,九谷焼の絵具として使用できるか検討した。
3.結 果
3.1 無鉛「九谷五彩」の開発
約600点の無鉛フリットを試作し,その中から透明性や耐酸性について検討を行い,九谷焼の和絵具に最適な無鉛フリットを選定した。
従来の酸化物を色素として無鉛フリットに使用した場合に,青(緑),紺青,紫において不具合が発生した。しかし,色素に検討を加えることにより,従来の鉛を含んだ絵具に引けを取らない無鉛「九谷五彩」を開発することができた。
従来の「九谷五彩」のうち黄,青,紺青,紫は透明性のある絵具であるが,赤は不透明な絵具を使用している。透明な赤の開発は,九谷焼の永年の技術的課題であり,ここでは,これまで作ることのできなかった透明でかつ無鉛赤の開発も行った。
このため開発した無鉛和絵具は,透明赤を含めると「五彩」ではなく「六彩」と言える。
3.2 技術移転
石川県工業試験場は,開発した無鉛和絵具を石川県九谷陶磁器商工業協同組合連合会へ技術移転した。現在では,透明赤も含めて無鉛和絵具が製造・販売されている。また,無鉛和絵具を使用した九谷焼製品も製造されており,平成16年9月に開かれた九谷焼産地大見本市では170点の無鉛製品が展示・販売された。
九谷焼は明治期に「ジャパン・クタニ」と海外から称され,貿易品として取り扱われていたが,現在では輸出量は大きく落ち込んでいる。業界では無鉛和絵具を使用した新製品を開発し,「ジャパン・クタニ」の再興を目指して海外販路拡大を模索している。
(図1 無鉛和絵具製品 )
(図2 九谷焼産地大見本市の無鉛和絵具製品 )