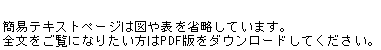
| 全文(PDFファイル:177KB、2ページ) |
| 玄米を用いた新清酒製造法に関する研究
|
||
| ■食品加工技術研究室 ○松田 章 道畠俊英 西村芳典 ■石川県酒造組合連合会 佐無田 隆 |
1.目 的
清酒製造における原料米処理工程では,玄米を30%以上削り(精米歩合70%以下),多量の米糠を排出している。玄米または精白度の低い米(低精白米)を用いて香味の良い清酒が製造できれば,米糠排出の抑制と省エネルギーにもつながる。しかし,玄米を用いて清酒を製造するには,米粒の溶解性の低さや玄米特有の臭い(特異臭)の点で課題がある。
本研究では,試作した焙煎装置を用いて,玄米及び精米歩合が100〜90%の低精白米について焙煎処理を行い,これらを掛米とした清酒を試醸し,香味に及ぼす影響を検討した。
2.内 容
2.1 原料及び原料処理
原料米は石川県産五百万石,麹は乾燥麹(徳島精工(株)製)を用いた。原料米の浸漬条件は,玄米の場合は15℃の水で15〜16時間,98%白米の場合は3時間,95%の場合は2時間,90%〜70%の場合は1時間とし,水切りを2時間行った。その後,蒸しまたは焙煎処理に供した。玄米を蒸す場合のみ,浸漬,水切り後,ロールミルO.S.K134(小川サンプリング(株)製,目開き1.5mm)で圧砕処理をしてから行った。焙煎処理は原料米を浸漬,水切り後,試作した米穀焙煎装置(図1)((有)村上商店製)を用いた。
(図1 焙煎装置の模式図 )
2.2 消化性試験
焙煎処理後の米の消化性を評価するために,日本酒度を指標とした消化性試験を行った。日本酒度の測定には,振動式密度比重計DA-500(京都電子工業(株)製)を用いた。
2.3 香気成分の測定
原料米の香気成分は,ガスクロマトグラフ質量分析計(GCMS-QP5050A,(株)島津製作所製)を使用し,TenaxTA(GLサイエンス(株)製)を用いたTCT法で分析した。また,清酒の香気成分の測定は,ヘッドスペースガスクロマトグラフ(HSS-4A+GC-17A,(株)島津製作所製)を用いた。
2.4 清酒の試醸
玄米及び,精米歩合98%,95%,90%,80%,70%の各白米を用い,蒸した場合と,焙煎処理を行った場合について,それぞれ清酒を試醸した。仕込配合の例を表1,表2に示す。
(表1 3段仕込みの仕込配合 (玄米・蒸し) )
(表2 3段仕込みの仕込配合 (玄米・280℃×6分焙煎) )
2.5 清酒の成分分析及び評価
試醸した清酒の一般成分の分析は,第4回改正国税庁所定分析法注解に準じて行った。有機酸分析には有機酸分析システムShodex OA(昭和電工(株)製)を用いた。なお,試醸した清酒は,パネラー7名による5点法(1:良,2:やや良,3:普通,4:やや悪,5:悪)で官能評価を行った。
3.結 果
3.1 焙煎処理条件と消化性
玄米を用いて,200℃〜300℃の範囲で時間を変えて焙煎処理を行い,得られた処理米の消化性を評価した。精米歩合70%の蒸米の消化性(日本酒度-46.07)に近い焙煎条件を選抜した結果,280℃で6分間が最適であった。
3.2 焙煎処理が米の特異臭に及ぼす影響
玄米臭の主成分は,1−ヘキサナール,1−ペンタノール,1−ヘキサノールで,これら3成分は焙煎によって未処理の玄米と比較して16.7〜3.9%に低減した。
3.3 試醸清酒の分析
試醸清酒の一般成分を表3に示す。有機酸の含有量で酸味の指標となる酸度は,精米歩合が高くなると高くなった。また,旨味の指標となるアミノ酸度は精米歩合が高くなると低くなった。
図2に,試醸清酒中の主な香気成分のうちイソアミルアルコール及びイソブタノールの含有量を示す。これらの含有量は,精米歩合が高くなると多くなった。また,清酒中の有機酸組成を図3に示す。図より明らかなように,リンゴ酸やクエン酸,コハク酸の含有量は,精米歩合が高くなると多くなった。
(図2 各清酒中の香気成分 )
(図3 各清酒中の有機酸組成 )
3.4 試醸清酒の評価
精米歩合を変えて蒸米及び焙煎米(280℃,6分間)で試醸した清酒について,官能試験(5点法)を行った。その結果,評点の平均はいずれも2.46〜2.96の範囲で,試醸清酒間の差は大きくなかった。しかし,精米歩合90%及び95%の焙煎米を用いて試醸した清酒が良い評価を得た。