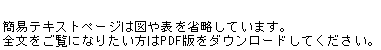
| 全文(PDFファイル:279KB、4ページ) |
| VRを用いたクレイアニメーション製作システムの開発
|
||
| ■電子情報部 ○米沢裕司 漢野救泰 橘泰至 中野幸一 |
1.目 的
クレイアニメーションとは,粘土で作った人形(図1)を少しずつ動かし,それをコマ撮りすることによって制作するアニメーションである。実写によるアニメーションであるため,その映像は粘土の色や影などが忠実に再現されており,映像のリアルさや独特の質感等から,高い人気を得ている作品も多い。その反面,粘土で作った人形を動かしたり,コマ撮りをしたりする作業はとても煩雑であり,クレイアニメーションの制作には膨大な時間を要している。
一方,VRはコンピュータを使って人間の五感に訴える人工的な環境をつくりだし,仮想の環境を対話的に体験できるようにする技術である。近年,VRは各種シミュレーション,医療・福祉用機器,アミューズメント用機器等において,基盤技術として活用されている。
本研究では,VR技術を応用することにより,従来,膨大な時間を要していたクレイアニメーションの制作を大幅に簡略化するシステムを開発した。本システムにより,コンピュータ画面上のクレイ人形を直感的な方法で動かしたり形や姿勢を変えたりすることが可能となる。また,形状データと写真データとの合成やコマ撮りを行うための機能も備えており,コンピュータ上で簡単にクレイアニメーションを制作することができる。
(図1 クレイ人形の例)
2.内 容
2.1 システムの構成
システムは,パソコン,触覚フィードバック装置(PHANToM Desktop) ,3次元カメラなどから構成されている(図2)。3次元カメラは物体の3次元形状を計測し,デジタルデータ化する装置である。本システムではミノルタ製VIVID700を使用しており,クレイ人形の3次元形状を簡単に計測することができ,計測したクレイ人形の形状データは,パソコンに転送される。なお,クレイ人形の形状は三角ポリゴン(多数の三角形の集合体)として取り扱っている。
PHANToM Desktopは,先端部がペン状になっており,これを手で握って使用する触覚フィードバック装置の一種である。パソコンからの制御に従って装置内のモーターが駆動し,3軸方向にトルクをかけることができ,任意の圧力(触覚)を手に伝えることができる。また,ペン先を動かすとその位置がリアルタイムにパソコンに入力される。
液晶シャッター眼鏡と赤外線エミッターは,モニターに映し出された映像を立体視するための装置である。液晶シャッター眼鏡をかけることにより,モニター上のクレイ人形が,あたかも目の前にあるかのように見える。
(図2 システムの構成)
2.2 クレイアニメーション制作のための機能
本システムでは,パソコン上で動作するソフトウェアを使用することによって,クレイアニメーションの制作を行う。以下にソフトウェアの機能を述べる。
2.2.1 形状データと写真データとの合成
クレイ人形の色や模様の再現性は,クレイアニメーションの品質を左右する重要な要素である。本システムでは,色や模様を実写の場合と同様に忠実に再現するため,3次元カメラで計測したクレイ人形の形状データとデジタルカメラで撮影した写真データとを合成する機能を備えている(図3)。
ユーザーは,クレイ人形を様々な角度からデジタルカメラで撮影し,その写真を本システムで読み込み,各々の写真を形状データに張り合わせる(テクスチャーマッピング)。この際,張り合わせの結果にゆがみなどを生じさせないために,写真と形状の位置や角度等を一致させる必要がある。そこで,本システムでは,ユーザーに写真上の任意の2点を選択させ,その2点が形状データのどの箇所に相当するかを指定させることによって位置合わせを行う。また,張り合わせの角度や位置の微調整機能を備えており,ユーザーは張り合わせの結果を随時確認しながら微調整ができる。
(図3 写真データの合成)(左:合成前,右:合成後)
2.2.2 形状変形
一般的なクレイアニメーションの制作においては,クレイ人形の形を手で変えながらコマ撮りを行っている。本システムでは,クレイ人形を手で変形させる場合と同様の直感的な方法で,パソコン画面上の形状データを変形させることが可能である。
形状変形の様子を図4に示す。パソコン画面上には3次元カメラで計測したクレイ人形の形状が表示されている。ユーザーはペンを持つような感覚でPHANToM Desktopを握り,手を動かすと,画面上のポインタが動く。このとき,手にはPHANToM Desktopから画面上のポインタとクレイ人形との位置関係に応じて圧力が伝わる。例えば,画面上のポインタとクレイ人形とが離れているときは圧力が伝わらず,自由に手を動かすことができるが,ポインタとクレイ人形が接触すると,手に対してクレイ人形の接触面の法線方向に圧力が伝わる。また,この状態からさらにポインタをクレイ人形に押しつけると,手に加わる圧力は増大し,画面上に表示されたクレイ人形がポインタの動き(手の動き)に応じて変形していく。このような圧力の変化やクレイ人形の形状変化は,粘土を手で触ったり押したりする感覚と極めて近いため,ユーザーは臨場感の高い形状変形を行うことができる。
(図4 形状変形の様子)
2.2.3 移動と回転
本システムは,画面上のクレイ人形の位置を変更したり,向きを変えたりするための機能を備えている。PHANToM Desktopを手で握り,画面上のポインタを動かすことにより,クレイ人形の位置を任意の場所に変更したり,任意の位置を中心に回転させたりすることができる。
2.2.4 形状補間機能
前述のように,従来のクレイアニメーションでは,クレイ人形の形状や姿勢を手加工によって変更しながら,随時コマ撮りを行うことによりアニメーションを制作していた。つまり,手でごく僅かに形状を変えながら,その都度撮影するという大変煩雑な作業が必要であった。
これに対し,本システムでは,ある形状とある形状の中間的な形状を自動的に補間する機能を備えているため,クレイ人形を変形させる前と後の形状データから,その中間的な形状データを作成することができる。本機能による補間の例を図6に示す。これは図5の変形前と変形後の中間的な形状を補間機能によって作成したものである。この機能により,ユーザーは1コマ毎に形状データを変更する必要がなくなり,作業性の向上と制作時間の短縮を図ることができる。
(図5 形状変形の例 )(左:変形前,右:変形後)
(図6 形状補間の例 )
2.2.5 画面キャプチャ
従来のコマ撮りに相当する機能として,画面キャプチャ機能を備えている。これはパソコン画面上の任意の範囲を画像データとしてハードディスク上に保存する機能である。また,上述の形状補間機能を利用しながら,連続的に画面をキャプチャすることもできる。なお,画面の背景は青色(ブルーバック)であり,市販のソフト等によって他の映像との合成を行うこともできる。
2.2.6 その他
本システムを用いたクレイアニメーション制作を行う際の補助機能として以下のようなものを備えている。
(1) 操作のやり直し(UNDO)
形状変形や移動等の操作を行った後に,その操作をキャンセルし,操作前の状態に戻すことができる。従来の手加工のクレイアニメーションでは,形状変形前の状態に戻すといったことは困難であったが,本システムではそれを容易に行うことができ,制作時間の短縮を図ることができる。
(2) 形状のスムージング
形状データ(三角ポリゴンの頂点座標値)を平均化することによってスムージングを行うことができる。クレイ人形全体はもとより,ある特定の箇所のみをスムージングすることもできる。
(3) 形状データの読み込み
DXF形式の形状データを読み込むことができる。3次元カメラで計測したデータのほか,市販の3次元CGソフト等で作成したデータの読み込みも可能である。
(4) 形状データの保存
形状変形等の作業中に,その形状を一時的にメモリ中に保存することができ,保存した形状は一覧表示したり,呼び出して再度形状変形を加えたりすることができる。また,ハードディスク上にDXF形式で保存を行うことも可能である。
2.3 クレイアニメーションの制作例
本システムを使用してクレイアニメーションの試作を行った。試作したものは,クレイ人形の口を動かしてしゃべるような動作をさせ,その後,画面上を動くという3秒程度のアニメーションである(図7)。
制作に要した時間は,クレイ人形の3次元形状データの取得に約2時間,ソフトウェア上での変形等に約20分であり,従来のクレイアニメーション制作方法に比べ,制作時間を半分以下に短縮することができた。また,出来上がった映像の質も,クレイ人形の質感を保っており,良好であった。
(図7 制作したクレイアニメーションの中の1コマの例 )
3.結 果
本研究では,VR技術を用いて迅速かつ簡単にクレイアニメーションを制作するためのシステムを開発した。このシステムによって,ユーザーは手で粘土を変形させる場合と同様の臨場感で,パソコン上でクレイ人形の変形を行うことができる。そして,写真データ等の合成,移動と回転,形状補間,画面キャプチャなどの機能を使用することにより,簡単にクレイアニメーションの制作ができる。
なお,本稿では,PHANToM Desktopを用いた形状変形等の操作について記述したが,操作性と臨場感を若干犠牲にすれば,入力デバイスとして3次元マウスや通常のマウスを使用することもでき,格段に安価なシステムを実現することができる。