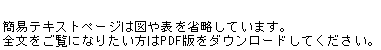
| 全文(PDFファイル:10KB、1ページ) |
| 酸素富化型有機汚泥溶融システムの開発
|
||
| ■株式会社アクトリー 水越 裕治* 増井 芽** |
■技術開発の背景
最終処分場等の不足が叫ばれる中,産業廃棄物は年間発生量約4億トン(H13年度実績)で変化なく,その約46.7%が「汚泥」で区分される廃棄物である。この中には,燃焼エネルギーを保有した汚泥があり,特に下水汚泥は脱水汚泥(含水率70-80%)の状態で搬出されており,これら下水脱水汚泥は,焼却及び灰溶融による処理方法が,大都市部や広域処理を実施している地方自治体で行われているが,低コストで地方地自体が維持管理できる処理場規模での脱水汚泥直接溶融炉の開発が求められている。平成13年度から15年度にわたり,石川県の委託事業として,石川県地域産学官連携豊かさ創造研究開発プロジェクト「多段蒸留方式による有機汚泥ゼロエミッション処理技術の確立」を行った。(プロジェクト参加機関:金沢大学,北陸先端大学,中部大学,石川県工業試験場,アクトリー,豊蔵組,互洋物産,管理法人:ISICO)
■技術開発の内容
① 人口2万人程度の乾燥汚泥重量換算で720トン/年程度の実証プラントを,50m2程度の敷地内で構築した。
② 脱水汚泥(70-80含水重量%)を1350℃に温度維持し,放熱を抑制溶融炉内に直接投入し汚泥中の有機成分の燃焼に必要な酸素は,酸素濃縮器PSA装置より供給した。
③ 排ガス処理装置は,2次燃焼室,熱交換器,バグファイルターより構成され,排ガス中のダイオキシン類の濃度は規制値を大きく下回る0.057 ng-TEQ/m3Nであった。
④ 脱水汚泥は,減容率で1/60を達成しており,溶融スラグからの規制物質の溶出量は酸性雨の影響を考慮した硫酸酸性(pH4)においても,基準を大きく下回っている。
⑤ 溶融スラグより試作したインターロッキングブロックは,50%程度まで混合しても,強度面では十分使用可能であった。
■製品の特徴
・ 濃縮酸素や保温構造の採用により実現した,小型・省エネルギータイプの脱水汚泥直接溶融炉である。
・ 炉温度の維持に必要な補助燃料を導入するだけで,脱水汚泥自身は自己を燃料として溶融する技術を構築した。
・ ランニングコストは,埋め立て処分費用以下である。
■今後の展開
下水汚泥処理への実機導入は,中長期の下水道事業計画があり時間を要すると思われるが,脱水汚泥をこれほどコンパクトなシステムで直接溶融した例はなかったのではないか。中小自治体,特に中山間地等で広域処理が困難な処理場への導入機運が高まる事を期待したい。今後,産業廃棄物における他の有機性汚泥の直接溶融についても活路を見出して行く予定である。