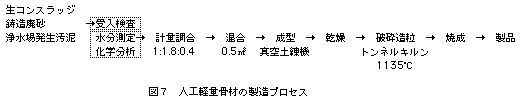
3.5.2 製造プロセス
実証規模における人工軽量骨材の製造プロセスを図7に示す。
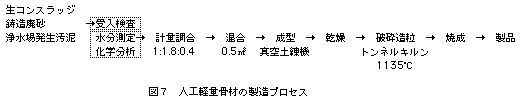
 破砕機で粗骨材の粒度に調整した試料を試作した自己燃焼炉(能力:1〜2ton/時 構造:バーナーを横又は上から点火し,メッシュベルト上に積層したグリーン体試料に着火させる。ベルトの下部から排ガスを吸引することにより,骨材が自燃して最高1100℃まで上昇する。)で焼成実験を行った。その結果,骨材を完全に脱炭素できるが,保持時間が短いために不均一な焼結にとどまった。
破砕機で粗骨材の粒度に調整した試料を試作した自己燃焼炉(能力:1〜2ton/時 構造:バーナーを横又は上から点火し,メッシュベルト上に積層したグリーン体試料に着火させる。ベルトの下部から排ガスを吸引することにより,骨材が自燃して最高1100℃まで上昇する。)で焼成実験を行った。その結果,骨材を完全に脱炭素できるが,保持時間が短いために不均一な焼結にとどまった。
3.5.3 製品の評価
自己燃焼炉で焼成した人工軽量骨材のIg.Lossは0,14〜0,22%でほぼ脱炭していることがわかる。
図7の製造プロセスで大量に製造した人工軽量骨材の長期評価は,JIS A 5002及び5308について日本建築総合試験所(吹田市)に依頼した。 図7より製造した人工軽量骨材の化学組成は,表10よりほぼ予想された化学組成になっていることを確認した。Ig.Loss及びSO3 の分析値はJIS A 5002の人工軽量骨材の品質試験に含まれている項目で十分規格に適合していることを確認した。
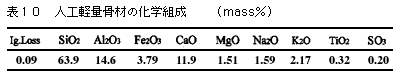
3.5.4 製造コストの試算
実証規模での運転実績から30000ton/年規模にした時の試算した人工軽量骨材のコストは約20〜22千円/tonになり,人工軽量骨材の市場価格は13〜14千円で推移していることから,図7の製造フローを見直して自己燃焼方式について再度検討が必要になっている。
3.6 応用製品の開発
 人工軽量骨材の需要は景気低迷により,高層建築の着工件数に比例して毎年減少している。そこで,自己燃焼方式で低コストで焼成した製品は,JIS規格に適合する人工軽量骨材と区別して,土木資材への応用が挙げられる。その一つとして,骨材をモルタルで固めた高付加価値な透水平板(300×300×60mm)を開発した。
人工軽量骨材の需要は景気低迷により,高層建築の着工件数に比例して毎年減少している。そこで,自己燃焼方式で低コストで焼成した製品は,JIS規格に適合する人工軽量骨材と区別して,土木資材への応用が挙げられる。その一つとして,骨材をモルタルで固めた高付加価値な透水平板(300×300×60mm)を開発した。
写真3は自己燃焼方式で焼成した人工軽量骨材で試作した透水平板を駐車場に敷設したもので,耐久性試験を実施している。その結果を踏まえて今後,商品化の方向で検討したい。
4.結 言
生コンスラッジ,鋳造廃砂及び浄水場発生汚泥を主原料にした人工軽量骨材の製造技術を確立した。この人工軽量骨材の原料となる各種の産業廃棄物の現状,研究開発の推移及び試作した人工軽量骨材の品質等について述べたが,以下に要約できる。
(1) 生コンスラッジは生コンクリート1m3当たり5〜10kgになる。骨材成型時に可塑材料として働き,成型後,自硬性を有しているので強固なグリーン体となる。生コンスラッジの化学成分は,概ねCaOとして40%以上を超えており,人工軽量骨材の原料に最適である。
(2) 銑鉄鋳物関係の生型砂における廃砂発生量は,製品1ton当たり215〜317kgであった。この鋳造廃砂は10%前後炭素を有しており,骨材の自己燃焼材料になる。
(3) 浄水場発生汚泥はポリ塩化アルミによる凝集沈殿汚泥でAl2O3として20%以上含んでいる。この汚泥は適正焼成温度領域の拡大と骨材中のCaOの含有量を調整する目的に最適であった。
(4) 基礎実験から人工軽量骨材の最適な混合比率は生コン1,鋳造廃砂1.8及び浄水場発生汚泥0.4であった。
(5) 最適焼成条件は1135℃で1時間焼成することにより,JIS A 5002及び5308に適合した人工軽量骨材が得られた。
(6) 試作した人工軽量骨材を用いた試し練り試験の結果,40N/mm2以上の圧縮強度となったので,高層建築素材として適用できる。破断面の観察ではモルタルと骨材との付着が良好なので粒界破壊がなく,破壊強度が大きい粒内破壊によって高強度化につながっていると考察される。
(7) 実証規模における製造プラントでの製造実験から,最も品質に重要な焼成工程を従来のトンネルキルン方式では燃費が高くなるので,自己燃焼炉を組み入れた新たな方式の検討が必要である。
(8) 人工軽量骨材を用いた応用製品として従来の製品と異なり,軽量でしかも透水性に優れた透水平板を開発した。現在,駐車場で耐久試験を実施中である。
謝 辞
人工軽量骨材の原料となる鋳造廃砂及び浄水場発生汚泥の試料を長期間にわたって提供して頂いた(株)梶鋳工所及び石川県鶴来浄水場に深く感謝します。
研究開発を進めるに当たり,焼成実験で施設の提供と多大なる協力を頂いた高砂工業(株)(岐阜県土岐市)の技術顧問永井 了氏(石川県技術アドバイザー)及び開発事業部主任 永冶良夫氏に又,生コンクリートスラッジの有効利用に関する多くの情報提供をして頂いた全国生コンクリート工業組合連合会 中央技術研究所 所長 鈴木一雄工学博士に深く感謝します。
参考文献
1) 廃棄物処理・再資源化技術ハンドブック,建設産業調査会,p21-28(1993)
2) 石川県,金沢生コンクリート,(株)特許2603599
3) 石川県,金沢生コンクリート,特願平8-321018
4) 濱崎和幸:セラミックス,Vol.32,p736(1997)
5) 鈴木一雄:コンクリートスラッジの有効利用に関するシンポジウム委員会報告書,コンクリート工学会,p8(1996)
6) 北村義治,坂本正司,本谷暢啓,塚林和雄,宮本正規,中村静夫:生コン技術大会 研究論文集,全国生コンクリート工業組合連合会,p161-166(1995)
7) 宮本正規,中村静夫,西村芳典:地域連携研究発表会講演論文集,p359-364(1994)
8) 中村静夫,宮本正規,塚林和雄:受託研究報告書,石川トライアルセンター,石川県工業試験場,p19-20 (1998)
9) 石川県手取川水道事務所,水質年報 第6集,p326-327 (1993)
10) 北村義治,坂本正司,宮前隆男,高島敏彦,塚林和雄,宮本正規,中村静夫:コンクリートスラッジの有効効利用に関するシンポジウム 論文報告集コンクリート工学会,p67-74(1996)
11) 化学便覧 応用編,丸善書店,p1096(1968)
|
|
|