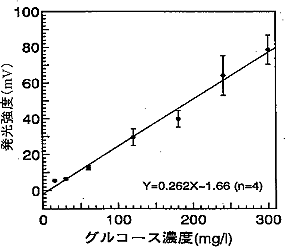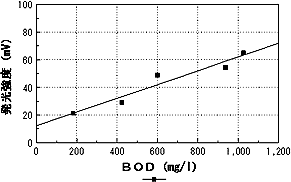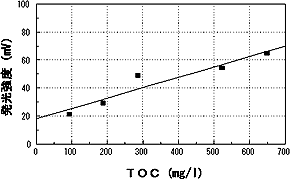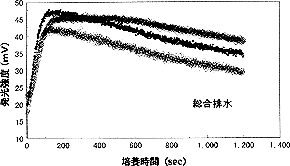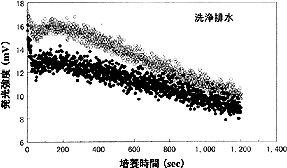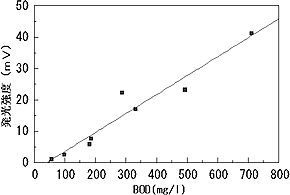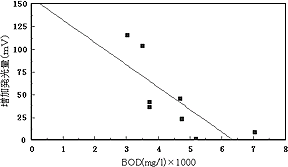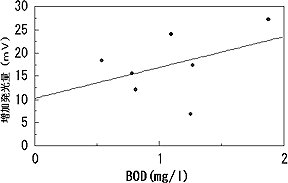平成10年度研究報告 VOL.48
発光原理を用いたバイオセンサによるBOD測定法 |
|
 |
3.結果と考察
3.1 標準溶液について
調整したD(+)グルコース標準液に対する発光強度測定を各濃度毎に4回繰り返し測定した。この際,最大発光量はわずか約7分で達した。
その発光強度は図4に示すように,D(+)グルコース濃度が高まるにつれてバラツキが大きくなる傾向にある3)ことが報告されている。
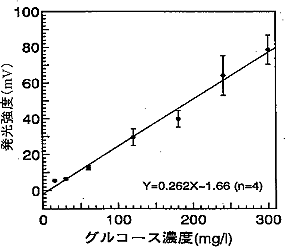 |
| 図4 標準溶液の濃度と発光強度との相関 |
3.2 活性汚泥処理した処理水について
BOD源に用いたグルコースは,活性汚泥に極めて資化しやすい材料の一つである。瀑気液を採取して東洋濾紙No.5Aでろ過した液について,3項目の水質を評価し,発光強度を基軸にBODとの相関及びTOCとの相関を図5,図6に示す。
本実験では活性汚泥処理水中には原生動物から細菌に至るまで多種類の微生物が生存しており,海洋性微生物が他の微生物の影響を受けるかどうかを確認する目的で行った。もし発光微生物が食物連鎖により,活性汚泥に資化されれば発光強度が全体的に低下することが予想される。
図4のグルコース300mg/lはBOD換算で概ね220mg/lである。その発光強度が80mVに達しているのに対して,図5より活性汚泥処理した処理水の発光強度は30mVとなる。このように図4に示す値に比較して1/3に減少しており,活性汚泥等の微生物による影響を受けていることが推察される。発光強度が全般的に低くなるが,各検水についてBOD-発光強度-TOCとの相関性が高いので,この検量線を用いることによって,発光強度からBODを短時間に推定することができる。
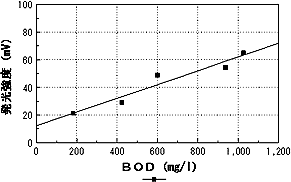 |
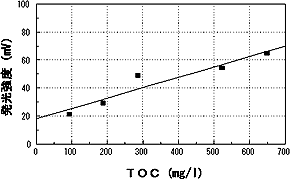 |
| 図5 BODと発光強度との相関 |
図6 TOCと発光強度との相関 |
3.3 産業排水への応用について
3.3.1 製造業種のバイオセンサの適合性
本システムの導入に最適な業種の絞り込みを行うため表3より20業種にわたって流入原水(適宜希釈)と放流水(無希釈)について測定した。
本システムに適した排水としては,資化しやすい絹精錬,和菓子,水産練り製品などの食品製造業,都市下水が挙げられる。
その一例として3回繰り返し測定した絹精錬排水(BOD 400mg/l)の発光強度は,図7に示すように27mV(3回測定の平均値)である。絹精錬排水には蛋白質の一種であるセリシンが溶解している。
一方,不適な業種としては忌避物質や資化しにくい物質が含まれる可能性の高いたばこ製造業,化学工業が挙げられる。2回繰り返し測定したたばこ製造排水(BOD
407mg/l)の発光強度は,図8に示すように数mVしか発光しなかった。このように発光微生物は資化源に対する選択性が強いことが報告されており4),10倍の差となって現れた。
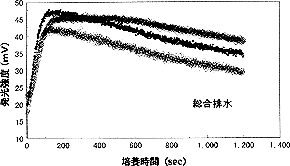 |
| 図7 絹精錬排水の発光曲線 |
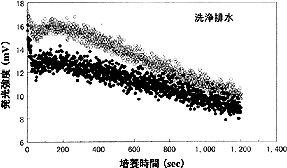 |
| 図8 たばこ排水の発光曲線 |
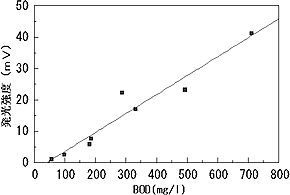 |
| 図9 製餡排水の発光強度-BODとの相関 |
3.3.2 4業種による追跡調査(その1)
第二段となるフィールド試験は,都市下水,菓子製造(製餡排水),染色排水(ポリエステルによる分散染料排水)及び廃棄物処理(廃油の油水分離工程等から発生する排水)の4事業所について流入原水と活性汚泥処理した処理水を対象に週1回の割合で3ヶ月追跡調査した。
水質測定は,採取したポリ容器(1L)で約10分間静置して粗いSS分を除去した上澄液について発光強度-BODとの相関を評価した。
4業種の流入原水の中で最も高い相関を示した例として和菓子工場の製餡排水について,その流入原水の発光強度とBODとの関係を図9に示す。
製餡排水や都市下水のように負荷源が安定さえすれば図9に示すように発光強度からBODを予測することが可能である。
廃油処理工場では廃油の油水分離工程から出る排水を活性汚泥処理を施して放流している。この流入原水のBODと発光強度との関係は,図10に示すように忌避物質の存在により,負の相関を示している。
正常な活性汚泥処理において処理水のBODは,通常10mg/l以下になる。このため,流入原水のように最小培地と検水の添加比率の9:1では発光強度が低くなることから,最小培地と検水の添加比率を1:1に高めて測定した。
図11より発光強度が高めることができたが,BOD及び発光強度の測定誤差も関与して相関が低く,処理水については発光強度からBODを精度高く推定することが困難である。
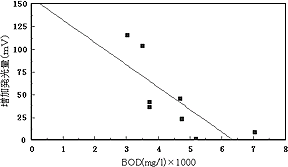 |
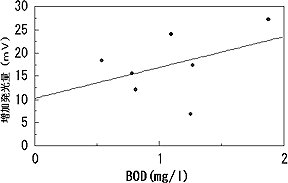 |
| 図10 廃油の油水分離工程からの流入原水 |
図11 同処理水の発光強度−BODとの相関 |
3.3.3 3業種による追跡調査(その2)
フィールド試験の第二段階での発光強度とBODとの相関は,標準試薬に比較して相対的に低い。その理由として,1)浮遊するSS分はBODに含まれるが,短時間で測定する同システムでは資化できない。2)浮遊するSSは散乱現象で発光強度を低下させる。以上の理由から,第三段階(最終)のフィールド試験としては,2.5.3項よりSSを除去した検水について評価した。
都市下水,製餡,染色の3事業所における流入原水及び放流水の発光強度-BODとの相関係数を表4に,発光強度-TOCとの相関係数を表5に示す。()内は測定件数
表4,表5に示すように第2段のフィールド試験で相関係数の低い流入原水の都市下水は,SS分をろ過することによって,発光強度−BOD,発光強度−TOC間の相関係数が飛躍的に向上する。しかし,菓子排水及び染色排水については大差ない結果となっている。
放流水の発光強度−BOD,発光強度−TOC間の相関係数は,ろ過しても全般的に低く,現状では発光強度からBODを推定することができなかった。
排水中に含まれる有機炭素(TOC)は全有機炭素測定装置で測定しており,複雑な操作を必要とするBODと比較して誤差が小さい。しかし,表4,表5の相関係数の比較で大差ないことから,低濃度の発光強度の誤差を小さくさせるための検討が必要となる。
表4 発光強度−BODとの相関係数
| 項目 |
都市下水 |
菓子排水 |
染色排水 |
流
入 |
ろ過 無
ろ過 有 |
0.312(9)
0.953(5) |
0.696(9)
0.665(5) |
0.751(5)
0.707(5) |
放
流 |
ろ過 無
ろ過 有 |
0.023(9)
0.966(4) |
0.019(8)
0.052(5) |
0.162(6)
0.047(5) |
|
表5 発光強度−TOCとの相関係数
| 項目 |
都市下水 |
菓子排水 |
染色排水 |
流
入 |
ろ過 無
ろ過 有 |
0.121(9)
0.868(4) |
0.553(9)
0.584(5) |
0.884(7)
0.904(5) |
放
流 |
ろ過 無
ろ過 有 |
0.145(9)
0.665(4) |
0.051(9)
0.033(5) |
0.333(5)
0.090(5) |
|
4.結言
海洋性発光微生物をバイオセンサとしたBOD評価方法の確立と,その信頼性について基礎試験及び3段階にわたるフィールド試験で検討し,次の結果を得た。
1)資化しやすいD(+)グルコースの標準溶液の濃度と発光強度は直線関係が得られるが,濃度が高くなるにつれて偏差が大きくなった。
2)バッチ式による活性汚泥処理で同標準溶液を資化した実験を行い,処理水の発光強度は同レベルのBOD濃度に比較して減少していることを確認した。
3)最大発光量に到達する時間は短い試料で5分,全体の測定に要する時間は20分以内となった。
4)海洋性発光微生物が資化しやすい工場排水として,絹精錬,食品(和菓子,水産練り製品,乳製品等),ランドリー,都市下水等が挙げられる。逆に微生物の阻害物質が含まれる可能性の高い化学工業,タバコ製造排水等は不適である。
5)廃油処理の油水分離工程から出る排水には微生物の忌避物質を含み,負の相関を示した。このように発光微生物によるBOD評価は,極めて選択性が強い。
6)資化しやすい流入排水については,発光強度-BOD直線からBODを推定することが可能である。しかし,低BODの放流水については,発光強度が小さいので,今後,発光条件の検討と菌体濃度の再検討が必要である。
7)本システムで評価するのに適した条件としては,常に対象となる製造物,加工物の変化が少ないこと。又,短時間でBODを多数測定する必要性がある事業所等である。
8)測定誤差が小さいTOCと発光強度との相関係数が発光強度−BODの相関係数との比較で大差ない結果となった。その原因としては,発光強度の測定の再現性に基因していると考えられ,発光条件の再検討が必要である。
謝辞
フィールド試験は県下の多数の企業のご協力をいただいて実施したものであり,ここに研究にご協力いただいた企業の方々に感謝します。
なお、本研究は平成8〜10年度の3年間にわたり,中小企業事業団の中小企業創造基盤技術研究開発事業で行いました。ここに関係の方々に感謝します。
参考文献
1)鈴木周一,軽部征夫,発酵工学,Vol.58,p.4209(1980)
2)松井暢人他,平成8年度 中小企業創造基盤技術研究開発事業研究成果報告書((株)イシメックス),プロジェクト番号8-11,p.2-3(1997)
3)民谷栄一他,平成9年度 中小企業創造基盤技術研究開発事業研究成果報告書(北陸先端大),プロジェクト番号8-11,p.2-3(1998)
4)宮本正規他,平成10年度 中小企業創造基盤技術研究開発事業研究成果報告書(石川県工試),プロジェクト番号8-11,p.3-12
(1999)