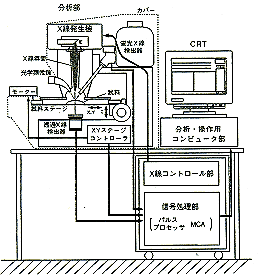平成10年度研究報告 VOL.48
漆器の分析技術の開発 |
|
 |
|
|
 |
漆器はもともと木に漆を塗ったものであったが,現在ではプラスチックに合成塗料を塗った近代漆器が主流となっている。また最近では,中国から安価な漆塗りの漆器が大量に輸入され,国内で加工販売されるようになってきた。これらの漆器を区別するために,さらには漆器の製造過程あるいは製品に生じるさまざまな欠陥の原因究明,クレーム対策のためにも漆器の分析技術が重要となる。そこで,さまざまな機器を使用して漆器の素材,製造工程,使用する材料などを判定することを目的に研究を実施した。そして,赤外吸収スペクトルデータベースを構築するとともに各種の顕微鏡を駆使して,材料や製造工程を容易かつ迅速に解析する手法を確立した。
キーワード:漆器,赤外吸収スペクトル,データベース,顕微鏡
Development of Techniques for Analyzing Lacquerwares
Toshiro EGASHIRA, Tachio ICHIKAWA
Originally a lacquerware is made of wood coated with urushi. However,
a modern lacquerwares made of plastics coated with synthetic paint become
the mainstream at present. In addition, a large quantity of cheap lacquerware
coated with urushi are imported from Chaina recently and those are sold
after processing. So an analytical technology of a lacquerware is significant
for distinguishing them, investigation of cause of various defects and
a claim countermeasure occuring in a manufacturing. The purpose of this
study is judging materials of a lacquerware and manufacturing processes
of it using the various instruments. Through constructing an infrared absorption
spectra database and utilizing various microscopes, we established a method
of analyzing materials of lacquerwares and manufacturing processes easily
and quickly.
Key Words :lacquerware, infrared absorption spectrum, database, microscope
1.緒言
漆器には木地に漆を塗った伝統的な漆器の他に, ABSなどのプラスチック素地にポリウレタン樹脂などの合成塗料を塗布した近代漆器があり,現在では近代漆器の方が多く生産されている。さらに中国(主に福建省)から輸入される廉価な輸入漆器がある。輸入漆器はほとんどが中国国内で調達した木地に漆を塗ってあり,プラスチック製漆器はまだ少ない。漆器の品質表示はまだ徹底されておらず,これらの漆器を一般消費者が区別するのはほとんど不可能である。安価なものを高価なものと不当表示して販売することが起こる可能性があり,実際に起こっている。これは漆器業界の信用に関わる問題であり,漆器の生産者のみならず消費者にも大きな損失を与え,漆器業界の衰退の一因ともなりうる。
そこでこのような問題を減らすためには漆器の分析評価技術を確立することが重要である。漆器のことを理解するためには,まずその原料である漆液のことを知らなければならない。漆液は主成分ウルシオールの他に水分,ゴム質,含窒素物(糖タンパク質)などから構成されている1)2)。漆は天然物で産地や採取した時期によって組成が変化し,その成分組成が漆液や漆塗膜の物性に大きく影響する。我々はこれまでに入手した漆液の成分組成,粘度,乾燥時間などを分析測定し,データベース化を行ってきた3)。このデータベースと多変量解析法(判別分析)を利用することによって漆の産地判定がある程度可能になった4)。さらに漆液の成分とその性質の関係についても明らかになった。それを基礎として漆器の分析評価技術について検討した。その手法としては,まず漆を含めた塗料,顔料,下地,素地などの既知物質について赤外吸収スペクトルを測定してデータベース化し,物質の判定を容易かつ迅速にした。また,X線分析顕微鏡,レーザー顕微鏡,あるいはファイバーマイクロスコープなどを用いて,塗装工程や塗膜欠陥の判定を行った。
2.実験
2.1 赤外データベースの構築
有機物あるいは一部の無機物は赤外領域にその物質特有の吸収を持ち,その物質の同定に利用できる。
使用機器:フーリエ変換赤外分光分析装置(図1)
・1650PC-DX型(パーキンエルマー製)
・FT-IR型顕微鏡
・IRデータマネージャー
・サドラーIRデータ集(スターターライブラリー, コーティングケミカルズ:12,900件)
赤外データベースを作成するために,漆器に使用される素地,下地,顔料,塗料などの赤外吸収スペクトル(波数範囲:4000〜450cm-1)を測定する。波数とは周波数や振動数と同じ次元で,
1cmの間に含まれる波の数でcm-1という単位で表す。測定法は主に試料と臭化カリウム(KBr)と混ぜて錠剤を成形して,その赤外吸収スペクトルを測定する錠剤法5)による。
IRデータマネージャーで測定データを規格化し,その吸収位置と吸収強度の一覧表(ピークテーブル)を作成する。測定データの解釈を実行し,試料の化学的な部分構造の解析を行う。測定データと解析結果を赤外データベースに登録する。この作業を繰り返して赤外データベースを構築する。
2.2 赤外データベースを用いた物質の同定
試料の赤外吸収スペクトルを測定する。IRデータマネージャーでピークテーブルの作成と化学構造の解釈を実行する。データベースをサーチして,試料のスペクトルに近いものを検索する。試料が純品か混合物か,またはサーチがピーク優先か構造解釈優先かを選ぶ。検索結果から最も近いスペクトルを重ねて表示し,一致するかどうかを確認する。一致するものがなければ,データベースに登録されていないので他の方法で検討する。その物質が何であるか明らかになった時点でデータベースに追加する。
 |
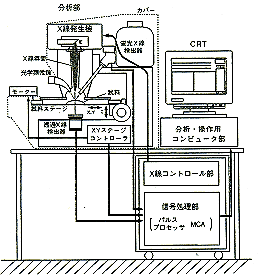 |
| 図1 フーリエ変換赤外分光分析装置 |
図2 X線分析顕微鏡7)のブロックダイアグラム |
2.3 ファイバーマイクロスコープによる観察
使用機器:マイクロスコープVH-6300(キーエンス製)倍率:1〜1,000倍
試料を簡便に観察可能で,断面の画像から膜厚の計測もでき,JPEG形式で画像の保存もできる。
2.4 レーザー顕微鏡による観察と測定
使用機器:走査型レーザー顕微鏡1LM21(レーザーテック製)
・画像処理ソフトSALT(三谷商事)
塗膜の表面形状を観察すると共に,2次元表面粗さを測定し,高さのヒストグラムとして分布状態を数値化する。試料の前処理が不要で,深い焦点深度が特徴である6)。微小欠陥の形状判定,刷毛目などによるうねり曲線の測定も可能である。
2.5 促進熱水試験
促進熱水試験機(田中科学機器製特注)を用い,熱水面(φ60mm)に漆塗りしたフェノール樹脂積層板(100×100×8mm)を当て,温度86〜90℃で80時間熱水試験を行う。
2.6 X線分析顕微鏡
使用機器:X線分析顕微鏡(堀場製作所製:図2)
XGTー2000V
試料に含まれる無機物(例えば,無機物を含む顔料や添加剤など)の判定に用いる。電子顕微鏡などと異なり導電処理などの前処理が不要である。