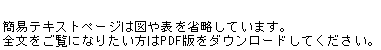
| 全文(PDFファイル:50KB、2ページ) |
| 文字フォントの加工による情報付加手法の開発
|
||
| ■電子情報部 ○林 克明 上田芳弘 ■金沢工業大学 梅原丈宏 山本 渉 岩田雅士 阿部武彦 ■金沢大学 木村春彦 |
1.目 的
ワードプロセッサなどで作成された電子文書の特徴の一つとして,複製や二次加工が容易であるという点が挙げられる。ただし,この特徴は文書の改ざんも容易であることを示唆しているため,電子透かしなどの情報ハイディング技術が利用されているが,これらの技術も印刷してしまえば,その情報は消失してしまう。紙の使用は,電子文書の増大によって減少しつつあるが,いくつかの利点により今後も継続使用されると考えられる。<br>
本研究では,従来の技術では困難であった印刷済みの紙文書に対する目視認証が可能な情報ハイディング技術を提案し,その有効性を検証した。
2.内 容
2.1 情報ハイディング技術の背景
情報ハイディングとは,情報を隠すためのセキュリティ技術全般を指し,一般には,電子透かしが知られている。これらの技術は,主に画像など冗長性のある,すなわち情報量の多いメディアを対象とする。文書の場合は,冗長性が少ないため適用例は少なく,さらに印刷された文書を対象とした情報ハイディング技術はほとんど報告されていない。
2.2 研究の概要
本研究で提案する情報ハイディングは,文字フォントへの切断加工を利用する。すなわち,文字フォントに対して図1のような切断加工を施し,この有無によって情報を表す。従来の情報ハイディングでは,ハイディング情報を第三者に認識されないようにすることが肝要とされており,通常はハイディング情報を目視認証することができない。しかし,本研究では,目視でハイディング情報を認証することを目指した。
今回実験の対象とした文字フォントは,ゴシック体フォントのひらがなとし,文字サイズは12ポイントとした。
(図1 切断加工を施した文字フォント )
2.3 研究の方法
本研究の有効性を検証するため,以下の項目で実験を行った。
(1) 切断加工幅の決定
文字に施す切断加工が,どの程度のサイズならば目視認証できるかを調べた。切断加工幅は,実寸ではなく,文字の線幅に対する切断幅の割合(図1中のB/A)で表現した。そして,実験のために切断加工幅が40%,50%,60%,70%の4種類の文字を用意し,80人の被験者を対象として実験を行った。実験では,420文字からなる文書を用意し,その中に20文字の切断加工文字をランダムに配置し,そのうちの認識できた切断加工文字数を計測するという方法を用いた。実験の結果から,60%を最適な幅として決定した。
(2) 埋込情報の抽出確認
上述の実験により,ハイディング情報の目視認証が可能であるという結果を受けて,実際に情報を埋込み,それを抽出することができるかを検証した。検証の実験方法は,約420文字で構成されている文書中に,10文字を埋込み,それを被験者に抽出させるということを3回行った。ハイディング情報の構成方法を図2に示す。18人を被験者として実験した結果を表1に示す。
(3) 被埋込文書の品質確認
本研究で提案する手法は,文字に切断加工を施し,その有無によってハイディング情報を表現する。このことは,元の文書の品質を低下させることと換言でき,また,ハイディング情報を伝達する相手にとってはさほど問題にならないが,ハイディング情報の存在を知られたくない第三者にとっては読むときの違和感の原因となったり,ハイディング情報の存在に気づかれたりする可能性が考えられる。そこで,切断加工文字について予備知識を有しない被験者を対象として,どの程度の影響があるかを検証した。
15人の被験者を対象として実施した結果,13人の被験者(86.7%)は切断加工に気づくことはなかった。この結果から,文字に施された切断加工が,文書全体の品質を低下させることはあまりないと考えられる。
(4) スキャナーに対する耐性
人間を対象とした場合,第三者が気づく可能性は,13.3%であったが,スキャナーとOCRソフトウェアに対する耐性についても検証した。実験には,切断加工を施したすべての文字フォントを対象として読み取りを行った。その結果,すべての文字は通常のすなわち切断加工がない文字として識別された。この結果から,OCRソフトウェアのような汎用ソフトウェアによる機械的耐性は十分であり,切断加工文字の存在を知られたくない第三者に対して,その存在が知られてしまうことは無いと考えられる。
(図2 埋込情報の構成 )
(表1 埋込情報の抽出確認実験結果 )
切断加工文字の平均誤視認数(個) 埋込文字の誤認識率(%)
文書1 2.9 17.8
文書2 1.0 10.0
文書3 1.8 8.9
3.結 果
ハイディング情報の目視認証が可能な文字フォントの切断加工による情報ハイディングという提案手法の有効性が確認できた。
提案手法では,文書中へ情報をハイディングした。本手法は,切断加工を施された文字を用いて情報をハイディングするものであり,文字が存在すれば,適用先は文書以外も考えられるため,文書以外にも応用できないか検討したい。また,現在は一文字ずつフォントを作成する必要があるため,ひらがなのみであるが,漢字や欧文フォントへの適用も検討したい。