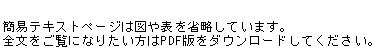
| 全文 (PDFファイル:407KB、4ページ) |
| 新県庁舎のユニバーサルデザイン
|
||
| ■ 製品科学部 ○前川満良 高橋哲郎 ■ 県リハビリテーションセンター 寺田佳世 ■ 県庁舎建設局 長谷川康之 |
1.目 的
新県庁舎は,「人にやさしい県庁舎」として誰もが安心して利用できる庁舎とすることを目指している。このため,車いす対応トイレ,エレベータ,案内・誘導用サインなどについて,障害のある人たちによる検証を踏まえて施工した。この検証を行うために,コーディネータとユーザ(車いす使用者,視覚や聴覚に障害のある人)で構成する「石川県庁舎建設施工ユニバーサルデザイン検討会」(平成13・14年度)を設け,これに工事施工者,設計事務所,県の担当者が参加して,高齢者や障害のある人への対応の幅を少しでも広げるための検討やサンプルの検証を行った。
本報告では,様々な配慮の中から視覚に障害のある人たちへの配慮点について紹介する。
2.内 容
2.1 視覚障害者の誘導について
視覚に障害のある人にとって,単独歩行は大きな課題である。この課題解決のために誘導用ブロックが開発され,広く普及している。しかし誘導用ブロックだけでは,十分な誘導ができるとは言い難い。誘導用ブロック以外の触知案内板,点字標示や音声誘導などを効果的に組み合わせることが必要である。新県庁舎ではこれらの要素を取り入れ,視覚に障害のある人の誘導にできるだけ配慮した。
(1) 誘導用ブロックと手すり
誘導用ブロックは床からの突起物となり,車いすの使用者や高齢者にとってはバリアとなることがある。そこで,手すりや壁で誘導できる経路では誘導用ブロックを敷設せず,手すりで誘導する手法をとり,誘導用ブロックを極力少なくする方針とした(図1)。
誘導用ブロックの敷設方法については,いくつかのガイドラインがある。しかし実際には,ほとんどがガイドラインにない応用課題であり,全庁舎の全経路について検討を行った。検討内容は,「最短かつ方向性を見失いにくい経路設定」,「エレベータ,トイレなどの誘導用ブロックを敷設しない場所で,誘導を引き継ぐ敷設方法」など数多く,仮設により何度も視覚に障害のある人と検証を行った(図2)。
(図1 誘導用ブロックと手すりによる誘導)
(図2 誘導用ブロックの敷設方法の検討)
(図3 誘導用ブロックと床の輝度比の検討)
また,弱視者への配慮も重要で,誘導用ブロックの見えやすさ,手すりの見えやすさを検証した(図3)。床のデザインの都合上一部見えにくい部分もあったが,一番見えにくい組み合わせでも輝度比1.5以上を確保し,建築上の基準をクリアしている。
(2) 触知案内板と点字標示
一般的に建物では,レイアウトを示す図面入り案内板がエントランスや各階に設置されている。これは目的の場所を探し,移動するためには欠かすことのできない設備である。しかし視覚に障害のある人にとっては,このような図だけから情報を得ることは困難である。そこで,触っても分かるように図面に凸凹や点字を配した触知案内板が徐々に普及し始めている。しかしこの触知案内板についてはガイドラインすらなく,点字さえ入っていれば良いといった無意味な触知案内板も多い。そこで,凸凹の度合い,廊下や居室の表現方法(触感に変化を持たせる方法),室名点字と墨字の配置,凡例の配置など非常に多くの事項を検討した。また,触れる高さで,誘導用ブロックや手すりとの連携も考慮しながら検討し,設置した(図4~6)。
新県庁舎ではエントランスや各階の触知案内板の他に,要望の強いトイレにも触知案内板を設置した(図7)。これは「便器に足を突っ込んだ」,「紙がないと困るので,紙の位置を知りたい」など,これまでの実体験の中から非常に苦労していたことに配慮した。
室名サインは一般に壁に設置されるが,誘導方法との連続性から手すりに点字標示を設置した。手すりにはこの他に分岐点での案内など,必要に応じて点字標示を設置した。手すりへの設置方法についても,触って読みやい位置で,点字の存在を見逃さないための検討を行った。「点字が一行の場合は手すりトップから1cm壁側に点字の最下点となる配置,点字が二行の場合は同じくトップから2㎜壁側に点字の最下点となる配置とする」といった統一ルールを決定し,このルールに従い,全庁舎の1000を越える全ての手すりに点字標示を設置した(図8)。
(図4 エントランスの触知案内板)
(図5 エントランス触知案内板の拡大)
(図6 視覚障害者による触知案内板の検)
(図7 トイレの触知案内板)
(図8 手すりに設置した室名表示の点字案内板)
(図9 フロア触知案内板の配色を検討)
(図10 音声誘導装置の特徴)
(図11 音声誘導装置の検証)
また,触知案内板は弱視や高齢者,色覚に障害がある人も見えやすいように配色についても検討(図9)を加え,健常者と共用できるものとした。
(3) 音声誘導装置
誘導用ブロックには注意喚起を示す点状ブロックと進行方向を示す線状ブロックの2種類しかなく,情報量が非常に少ない。そこで音や声による誘導を補助する装置がいくつか開発されている。しかしどの装置も一長一短があり,新県庁舎では屋外から玄関への誘導には池野通建社製「おんせい」,建物内部の誘導には三菱プレシジョン製「トーキングサイン」を組み合わせることで対応した。
いずれも建物に設置された受信機と手元の送信機により,音声誘導を行う。前者は建物に設置された受信機のスピーカーが声を出す方式で,必要としない人にも聞こえるため騒音が課題となる。一方後者では,手元の送信機で案内が聞けるためこの問題は解決される。さらに,接近方向によって異なったメッセージが送信できるため,きめ細かな誘導が可能となる。(図10,11)
2.2 設備の工夫
新県庁舎内に配置された設備にも,視覚に障害のある人への配慮を検討した。
(1) エレベータ
行政,警察,議会の庁舎を合わせると計4社のエレベータメーカが採用されている。視覚に障害のある人にとって操作方法の不統一,情報の不足が課題として挙げられた。そこで,ボタンの配置,形状などを検討し,検討結果を全てのエレベータで統一した。工夫点は以下の通りである。
・ 全ボタンに点字標示し,触読しやすいボタンの位置とした。(図12)
・ 階数表示ボタン内の数字を浮き文字とした。(図13)(点字を読めない人への配慮)
・ 階数ボタンをブロック分けし,数多くのボタンからの選択が容易になった。(図14)
・ 予約と到着が区別できるように音を分けた。
(図12 操作パネルへの点字サインの付加)
(図13 操作パネルのボタンを浮き文字化)
(図14 ブロック分けされた操作ボタン)
(図15 VODシステム概観)
(図16 初期画面)
(図17 画面下縁のボタンで操作する様子)
・ チャイム音により最大4機のどれが到着し,さらに上行き,下行きであるかを識別できるようにした。
(2)VOD(ビデオ・オン・デマンドシステム)
県政情報をビデオやクイズで提供するビデオ・オン・デマンドシステム(図15)が1階と19階に設置された。当初の計画では操作はタッチパネルだけで,画面上のボタンを選びながら100以上のビデオから希望するビデオを選択するシステムであった。しかし,視覚だけでしかボタンの位置が分からないタッチパネルでは,視覚に障害のある人には全く操作できない。そこで,金沢工業大学水野舜教授と共同で進めている「視覚障害者のためのタッチパネル操作方法の研究」の成果の一部を導入した。操作方法は,タッチパネル上で触るのは画面下縁に用意した4つのボタン(メニュー,前へ,次へ,決定)だけで,音声ガイダンスに従いながらこのボタンを押すことでビデオが選択できるようになった。(図16,17)
(3)電光表示板システム
エントランスホールに,会議,イベントなどの場所,時間を表示する電光表示板システムが設置されている。壁面の電光表示だけでしか情報が提供されない課題があった。そこで視覚に障害のある人のために音声誘導装置「トーキングサイン」と連動させ,表示内容を手元の受信機で聞き取れるようにした。電光表示板と音声誘導の担当部署が異なり,孤立したシステムになる危険性があったがユニバーサルという別視点での見直しにより,連動したシステムが可能となった。
3.結 果
視覚に障害のある人とともに検討・検証し,採用できる部分はできるだけ採用した。しかし,建物の構造やデザイン性のため,或いは十分な機能の設備がないために案だけで終わった点もあり,新県庁舎が100点満点とは言い難い。しかし,現時点の建物として県視覚障害者協会からも高い評価を戴いた。
誘導方法については,まだ体系的なまとめができていないため,ガイドラインの作成にいたっていない。しかし,経験の少ない設計者,工事施工者でも有効な誘導方法を導入できるようにするためには重要であり,今後はガイドラインの整備を進めていきたい。
最後に,検討・検証にご協力いただいた検討委員会,工事施工者の方々と検討のたたき台作成にご協力いただいた『視覚障害者の誘導を考える会』の皆様に深く感謝いたします。