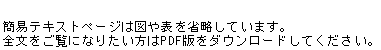
| 全文(PDFファイル:104KB、1ページ) |
| 視覚障害者用の携帯型色認識装置の開発 −自動校正機能による測色安定性の向上− |
||
| ■電子情報部 ○前川満良 ■(株)北計工業 橋爪慎哉 當間安厚 有谷秀明 ■レハ・ヴィジョン(株) 一二三吉勝 ■金沢大学工学部 関啓明 |
研究の背景
視覚障害者は,晴眼者を介さずに色を認識することが難しいため,日常生活で不便を強いられることが多い。例えば,「左右で異なった色の靴下を履いていたために,恥ずかしい思いをした」といった経験などから,「色を知るための道具」の開発が望まれている。そこで本研究では,視覚障害者が色を認識するために必要十分な精度を有し,多くの色をわかりやすく表現できる色認識装置を開発した。
研究内容
開発した装置は,大きく分けて色を測定する測色部と測定値を色名に変換し色名を音声化する色表現部から構成されている。
測色部では,携帯型にすることによって,環境の変化や落下による光学系のズレなどが測定に影響を及ぼすことから,その対策として自動校正機能を提案し,その有効性を検証した。実験の結果,温度変化に対する測定値の変動の最大値は1/3以下に,光源も15%の光量変動に対して1/7以下になり,測定の安定性が向上した。また,物を探すことを不得手とする視覚障害者にとって,校正機能を装置外部に持たせるのは不便なことから,校正用の色試料を装置に内蔵する方法を検討した。その結果,複数の色試料を円盤状に配し,操作レバーと連動する実装方法を開発した。
測定により得られるRGBの数値データでは色を想像しにくいことから,色表現部ではRGBから色の3属性であるHLS(色相,明度,彩度)へ変換し,さらに,明度・彩度に対する修飾語,色相に対する修飾語,基本色名といった色に関する言葉を組合せた220種類の色名へ変換する方法を開発した。
(カラートークの概観)
研究成果
本研究では,視覚障害者が色を認識するための携帯型色認識装置を開発した。これにより,視覚障害者は次のようなことが可能となった。
(1) 色を220種類の色名に変換し,音声で出力することで容易に色を認識することが可能となった。
(2) 小型化により携帯が可能になり,外出先でも色を認識することが可能となった。
(3) 自動校正機能により,温度変化や光源の変化に対する測色精度の向上を検証した。
(4) 校正用色試料を装置に内蔵し,操作レバーと連動することにより校正の煩わしさがなくなり,認識時間が0.1秒以下になった。
論文投稿
精密工学会誌 Vol. 69, No. 11, 2003. p.1648-1653.