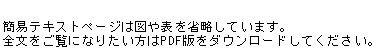
| 全文 (PDFファイル:515KB、6ページ) |
|
古紙を原料とする発泡体の開発
|
||
| ■
舟木克之* 七山幸夫* 新保善正** 松本健*** 廣瀬幸雄*** 山田僖幸**** *機械電子部 **繊維部 ***金沢大学 ****日拓産業㈱ |
近年,木材繊維等のセルロースをポリオール系溶媒で液化し,イソシアネートとの重合反応で発泡させるバイオマスプラスチック製造技術が開発され,石油系プラスチックに代わる技術として注目されている。本研究では,余剰古紙の他用途利用促進のため,新聞や雑誌等の低級古紙を液化し,天然高分子発泡体を得る製造方法について検討した。その結果,①ポリエチレングリコール系溶媒を使用し,古紙をマイクロ波で70~80℃に加熱することにより,古紙の液化物を得ることができる,②液化古紙はイソシアネートと攪拌混合することにより発泡し,攪拌速度が速いほど,また液化古紙の温度が高いほど発泡・硬化時間が短くなる,③新聞紙を原料とした発泡体よりもチラシ等のカラー印刷物を原料とした方が圧縮硬さは高く,特に新聞紙とチラシを1:1で混合した場合,発泡スチロールを上回る硬さが得られることなどが明らかになった。
キーワード:古紙,発泡体,ウレタン反応,セルロス液化,圧縮硬さ,リサイクル
Preparation of the Foam Block using Waste Paper
Katsuyuki FUNAKI, Yukio NANAYAMA, Yoshimasa SHIMBO, Ken
MATSUMOTO, Yukio HIROSE
and Yoshiyuki YAMADA
Recently, using the liquefaction of cellulose, such
as a wood fiber, the biomass plastics manufacture technique is developed. In
this technique, a foaming is carried out by an isocyanate polymerization reaction
using a polyol as a solvent. It is expected as a new plastic manufacturing method
alternative to petroleum system. In this study, in order to accelerate the other
applications of surplus waste paper, we examined a preparation method that involved
naturally occurring polymer foam using low-grade used paper, such as newspapers
or magazines. The main results obtained are as follows; (1) Polyethylene-glycol
system solvent can be acted and the liquefaction of waste paper can be obtained
by heating the paper at 70 to 80 ℃ with a microwave. (2) The foaming of paper
liquefaction is carried out by churning mixture to the isocyanate, and if churning
velocity is large or a temperature of the process is high, a foaming and a cure
rate becomes quick. (3) The foam made from color printed papers showed higher
compression hardness than the case of newspapers. Especially, when a newspaper
and advertising paper are mixed by 1:1, the hardness more than styrene foam
was obtained.
Keywords:waste paper, foam, urethane reaction, liquefaction of cellulose, compression
hardness, recycle
1.緒 言
新聞や雑誌等の古紙は,古くから回収システムが確立され,ダンボールや印刷紙等に再利用されている。しかし近年,リサイクルに対する社会的関心が高まるにつれ,回収される古紙が過剰となり,雑誌、チラシ等の低級古紙が回収されずに可燃ゴミとして焼却されている。けれども古紙の製紙原料への利用では大幅な増加が見込めないため,森林保護の観点からも古紙の他用途利用技術の開発が重要である。
近年,木材繊維から取り出したセルロースを液化1) し,発泡体を製造する技術が開発2)され,緩衝材や断熱材に応用する試みがなされている。古紙もセルロースを効率よく含んでおり,同手法による発泡体用材料としての使用が可能と考えられる。しかも天然高分子のセルロースは,微生物による酵素分解性を有しているため,発泡スチロールに代わるエコ材料として期待できる3)が,実用化には至っていない。そこで本研究では,ポリオール系有機溶媒で液化した古紙の発泡剤にイソシアネートを使用し,反応物の組成割合や反応温度等発泡体製造条件の系統的な実験や,圧縮硬さや吸水率等の物性評価を行い,古紙発泡体の実用化を達成する基礎研究とした。
2.内 容
2.1 古紙発泡体の作製
反応表面積を大きくし,反応を容易にする目的で,古新聞を乾式解繊機で綿状パルプ化し,ポリエチレングリコール,グリセリン,98%濃硫酸を加えて混合・攪拌しながら,マイクロ波を用いて70~80℃に加熱するとセルロースの液化反応により,図1に示すような比較的流動性の良い黒色液化物が得られた。この液化物をA液と呼ぶ。強酸性のA液を中和するための苛性ソーダ,発泡触媒,整泡剤からなるB液と混合することで化学的に安定となり,液化古紙原料として保存できる。液化古紙にジイソシアナート(C液)を混ぜ合わせて攪拌すると,炭酸ガスを発生しながら発熱反応し,発泡体が得られる。この時のA,B,C液の割合は表1に示すとおりである。
2.2 液化古紙の組成分析
古紙発泡体の主成分は有機物であるが,インク顔料や製紙時の添加剤が混入しているため,廃棄した際に残留する無機物の種類や量を見積もっておく必要がある。液化古紙を1000℃で強熱減量した結果を表2に,灰分の蛍光X線分析結果を図2に示す。その結果,液化古紙の強熱減量後の灰分量は1.7%前後であり,その化学組成はカルシウム,珪素,イオウが多く,その他金属元素のアルミ,鉄,亜鉛,チタン等が含まれるが,環境に負荷を及ぼす重金属類は検出されなかった。ここで,灰分中のカルシウムはセルロース中に含まれており,イオウは古紙の溶媒中に含まれる硫酸から,珪素は製紙時の添加剤によるものと考えられる。
2.3 古紙発泡体製造条件
2.3.1 攪拌条件の影響について
表2 液化古紙の強熱減量
液化古紙量(g) 灰分量 (g) (%)
8.123 0.137 1.68
3.942 0.068 1.73
図2 液化古紙灰分の蛍光X線分析結果
図1 古紙液化物
表1 材料の配合割合
薬品名 重量(g) 役 割
A 液 古紙 100 セルロース
ポリエチレングリコール 210 溶 媒
グリセリン 90
98%濃硫酸 9
B 液 48%苛性ソーダ 6.1 中和剤
K-305M1) 4.1 整泡剤
KS12602) 4.1 発泡触媒
A+B 423.3 液化古紙
C 液 ジイソシアナート 323.1~749.4 発泡剤
1)信越化学工業製 2)共同薬品工業製
500mlの紙コップに表1の液化古紙(A+B液)を42g計量し,これに重量比で1.06倍のジイソシアナートを加え,2分間プロペラ攪拌機で混ぜ合わせた際の攪拌速度が、発泡反応の開始と終了時間に及ぼす影響を図3に示した。なお,この時の室温は22℃であり,反応時間は攪拌を開始直後から計測した。図より,発泡(重合)反応は攪拌速度に大きく依存することがわかる。また,この時得られた発泡体の状態を図4に示す。攪拌速度300rpm以下では成形体が得られておらず,均一な発泡体を得るためには,反応物を短時間に攪拌混合するが必要である。
図3 発泡反応に対する攪拌速度の影響
図5 発泡反応に対する攪拌時間の影響
液化古紙とジイソシアナートの混合状態が発泡に大きく影響することから,図4で均一な発泡体が得られた攪拌速度500,600rpmの条件で,攪拌時間を変化させた結果を図5に示す。攪拌速度600rpmでは発泡終了時間が7分と一定であり,1分間の攪拌でも反応物の混合が十分に行われたものと考えられる。一方,500rpmでは攪拌時間とともに反応時間が早くなり,600rpmの反応終了時間レベルに達するまで4分の攪拌が必要であった。
2.3.2 各種薬剤の影響について
表1の配合割合において,中和剤の苛性ソーダ(NaOH)を0~11.5g(液化古紙の2.7wt.%)の間で変化させた場合の古紙発泡に対する影響を図6に示す。なお,ジイソシアナートは,液化古紙に対して重量比で1.38倍添加し,原料の攪拌は600rpmで2分間行った。発泡開始時間がNaOHの添加量増加とともに早くなり,密度は小さくなる傾向を示した。密度の変化は発泡倍率の変化であるため,発泡体の物性は,NaOH量によりある程度の制御を加えることが可能であるが,発泡体の用途を考えた場合,中性であることが望ましい。
遅い ← 撹拌速度 → 速い
図4 液化古紙の発泡状態
次に発泡触媒を0~12.0g(液化古紙の2.83wt.%)の間で変化させた時の影響を図7に示す。ここで,中和剤の添加量は6.1gとし,その他の条件はNaOH量の実験と同じである。
発泡触媒を全く添加しない場合では反応終了まで21分もの時間を要し,良好な発泡体が得られなかったが,発泡触媒を少量添加することにより反応時間は2/5に短縮された。また,添加量が0.63~0.98wt.%の間では,反応開始から終了までの時間(反応時間)が8分と一定の値を示し,それ以上の添加では,反応時間が触媒添加に伴って短くなった。触媒添加0.35~2.21wt.%の間では,発泡体の比重が0.044g/cm3程度とほぼ一定であり,この範囲内で反応時間を制御した発泡古紙の製造が可能であることがわかる。しかし,添加量が2.83wt.%では十分な発泡が得られないまま硬化したことから,1wt.%前後が適当と考えられる。
図6 古紙発泡に対するNaOHの影響
図7 古紙発泡に対する発泡触媒の影響
図8 古紙発泡に対するジイソシアナート量の影響
発泡剤のジイソシアナートは,発泡古紙の原料中で最も使用量が多く,また高価な薬剤であるため,その添加量はできるだけ少ないことが望ましい。そこで,表1に示す配合で,古紙発泡に及ぼすジイソシアナート量の影響を調べた結果を図8に示す。なお,攪拌条件は,600rpm,2分間とした。いずれの場合も発泡開始までの時間は3分前後であったが,ジイソシアナート/液化古紙(ジイソシアナート比)が0.76では,十分な発泡が得られなかった。ジイソシアナート比が1.08~1.39では,比重が0.045g/cm3程度の良好な発泡体となった。また,ジイソシアナート比が1.77と高い場合では,発泡終了までの時間が長いため,製造上扱いやすいが,比重が0.01g/cm3程大きくなった。
2.3.3 古紙発泡に対する液温の影響
前項の実験で,添加薬剤の加減によって発泡反応時間をコントロールできることが明らかになったが,同時に発泡体の性状も変化させてしまうため,薬剤組成を一定にして発泡反応をコントロールする必要がある。発泡反応は発熱反応であるため,液化古紙やジイソシアナートの液温により反応開始時間の制御が可能と考えられる。そこで,表1の配合割合を用い,液化古紙に対するジイソシアナート比1.38,攪拌速度600rpmの条件下で,液温が発泡反応に及ぼす影響について調べた結果を図9に示す。なお,前項と同様に攪拌時間は2分としたが,液温が高い場合は発泡反応が2分以下で始まったため,30℃以上では攪拌時間を1分とした。
図からわかるように,発泡反応の開始と終了時間は,液温の上昇と共に短くなり,30℃以上では飽和する傾向にあった。また,液温12℃と35℃では反応開始時間が4倍違っており,工業的に生産する場合には,夏場と冬場で成形のためのサイクルタイムが異なることになる。しかし,発泡高さ(倍率)がほぼ一定であり,供給液温の制御による方法が実用的な反応時間コントロール法と考えられる。
2.4 古紙発泡体の物性
一般に古新聞は,チラシ等のカラー印刷紙が同時に回収される。カラー印刷紙はその機能上,粘土質の無機物で表面コーティングされており,また,インクは化学物質であるため,これらが相当量混入すると古紙の液化・発泡反応に何らかの影響を及ぼすものと考えられる。そこで,物性評価ではこのことを考慮し,新聞液化古紙に1.5倍のジイソシアナートを加えたもの(試料A),新聞液化古紙に等量のジイソシアナートを加えたもの(試料B),新聞50%+チラシ50%液化古紙に1.5倍のジイソシアナートを加えたもの(試料C)の3種類について,500×500×45mmの密閉型中で発泡成形した。なお,物性評価試験については,JIS
K6767にある発泡ポリエチレンの試験規格4)を適用した。
図10 発泡体の見かけ密度
(a) 試料A
(b) 試料B
(c) 試料C
図11 発泡セルの構造
2.4.1 型成形発泡体の見かけ密度について
図9 液温が発泡反応に及ぼす影響
体積が15cm3以上になるように立方体を切り出し,ノギスで寸法測定後,電子天秤で質量を測定して見かけ密度を求めた結果を図10に示す。それぞれの試料について5個づつ測定し,その平均値を採用した。
ジイソシアナート量の少ない試料Bでは,見かけ密度が0.0075g/cm3と一番大きくなった。また,同じ新聞液化古紙を使用しても,ジイソシアナート量を1.5倍加えた試料Aでは,0.0047g/cm3と3つの試料中で最も小さくなったが,緩衝用発泡スチロールの値(0.002g/cm3)よりも大きい。一方,粘土質が混入する試料Cでは,試料Bと同じく見かけ密度が大きくなった。
見かけ密度の違いを調べるため,図11に発泡体断面のセル構造をSEMで観察した結果を示す。密度の小さな試料Aでは,見かけ密度の大きい試料B,Cと比べて発泡セルが大きく,発泡反応中に炭酸ガスが多量に発生したことがわかる。一方,同じ分量のジイソシアナートを添加しても,粘土質やカラーインクが混入する試料Cではセルの大きさが不均一であり,発泡反応が混入物により阻害されたものと考えられる。
2.4.2 古紙発泡体の強度について
JIS規格に準拠して,引張試験片(平行部寸法:40×10×10mm)と圧縮硬さ試験片(50×50×25mm)を5個づつ作成し,島津製オートグラフを使用してそれぞれの強度を求めた。なお,引張試験片ではチャック切れを防ぐため,掴み部に1mmのアルミ板をエポキシ接着剤で貼り付けて補強した。試験結果の平均値を表3に示す。表中には参考として,発泡倍率55倍の発泡スチロールの弾性率と圧縮硬さの値も示した。見かけ比重の最も小さかった試料Aでは,発泡スチロールの圧縮強度に比較して弱く,緩衝材用途には向かない。しかし,図11(a)に見られたように空孔が大きく,断熱材等の用途に適していると考えられる。一方,試料Cでは引張強さや圧縮硬さが大きく,弾性率も発泡スチロールに近いため,緩衝材用途に適した特性である。
2.4.3 古紙発泡体の吸水性について
図12 各種発砲対の吸収率
JIS規格に準拠して,全面が切断面となるように100×100×20mmの試験片を作成し,試験片が完全に水没した状態で24時間放置後,エタノール中に5秒間浸せきし,60℃で5分間の表面乾燥を行い,重量測定した。その後,60℃で24時間の完全乾燥を行い,表面乾燥時の重量との変化の算出により,発泡体内部の吸水量とした。試験片はそれぞれ3個づつ使用し,その平均値を図12に示す。高強度の試料Cでは,吸水率が0.0027g/cm3と最も小さい値であった。これは発泡スチロールの約半分の値であり,長期間使用してもカビやダニが発生しにくいと推測される。しかし,見かけ密度が同程度であった試料Bの吸水率は,0.0093g/cm3
と試料Cの3倍以上も高かった。これは図8に示したように,ジイソシアナート量が少ないと反応開始から終了までの時間が短く,発泡セルが独立して存在せずにつながってしまったものと思われる。
3.結 言
セルロースの液化反応を利用し,古紙発泡体を製造する技術開発を行った。得られた主な結果は,次の通りである。
(1)ポリエチレングリコール系溶媒を使用し,古紙をマイクロ波で70~80℃に加熱することにより,古紙の液化物を得ることができる。
(2)液化古紙はイソシアネートと攪拌混合することにより発泡し,攪拌速度が速いほど,また液化古紙の温度が高いほど発泡・硬化時間が短くなる。
(3)新聞紙とチラシ等のカラー印刷物を1:1で混合した古紙を原料とした発泡体は,圧縮硬さや吸水率で発泡スチロールを上回る物性が得られ,代替緩衝材として使用できる。
参考文献
表3 各種発泡体の強度
試料名 引張強さ(kPa) 弾性率(MPa) 圧縮硬さ(kPa)
A 115 1.0 102
B 158 3.2 118
C 503 4.8 168
発泡スチロール - 5.9 135
1) 白石信夫,田村靖夫,辻本直彦:木材工業, Vol.43-1, p.2-6 (1988)
2) 白石信夫:バイオプラスチックのすべて,工業調査会 (1993)
3) 白石信夫,吉岡まり子,桃 耀廣,猪塚昭博,藤井賢治, 梶川泰照:平成8年度独創的産業技術研究開発促進事業プロジェクト成果報告 (1996)
4) 日本工業規格:発泡プラスチック-ポリエチレンの試験方法, 日本規格協会, JIS K 6767