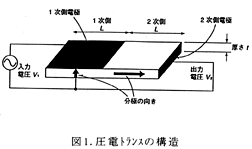
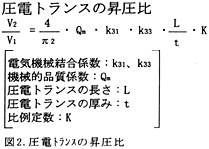
|
2.1 実験方法
実験方法を表1に示す。セラミックス原料には、マンガンを微量添加し、スプレードライヤー処理を行った市販のチタン酸ジルコン酸(以後PZTと略す)を使用した。原料粉末はプレス法にて円柱状に加圧成形し、マグネシア坩堝に入れてジルコン酸鉛の鉛過剰雰囲気で、1240℃近辺で電気炉にて焼成した。なお降温時に1040℃で焼き鈍し(アニーリング)を行った。
焼結体は所定の形状に切り出した後、銀電極を750℃で焼き付けた。その後、電極の両端に直流電界を印加し分極処理を行った。分極後のサンプルは短絡した状態で、4時間150℃の恒温槽でエージングを行った。圧電トランスも上記と同様の方法で作成した。
圧電特性はインピーダンスアナライザーで測定した。機械的強度は日本工業規格(JIS R1601)に準じて4点曲げ試験機で測定した。結晶構造はX線回折装置で、焼結体の表面微構造は走査型電子顕微鏡(SEM)で測定した。
| セラミックス原料 | チタン酸ジルコン酸鉛(PZT) |
| 焼成条件 | 1240℃(焼結)、1040℃*5時間(焼き鈍し) |
| 電極焼き付け | 銀ペースト、750℃*10分 |
| 分極条件 | 直流電界、3kV/mm*30分 |
| 圧電特性評価 | インピーダンスアナライザー(HP-4192A) |
| 材料特性評価 | 4点曲げ強度試験装置 粉末X線回折パターン測定装置 走査型電子顕微鏡装置(SEM) |
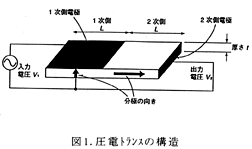
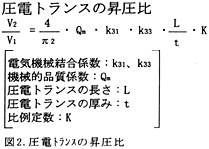
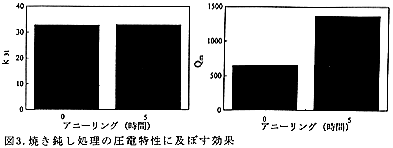
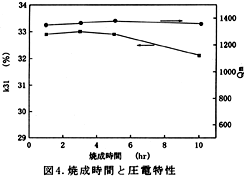
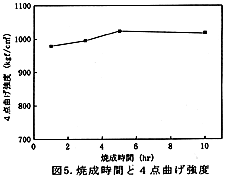 2)機械的強度
2)機械的強度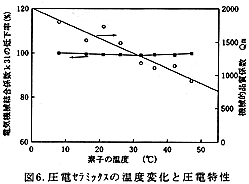

謝辞
本研究を遂行するにあたり、ニッコー株式会社に多くのご助言を頂きました。ここに感謝の意を表します。
参考文献
1)日経エレクトロニクス,147-57,1994
2)内野研二,圧電/電歪アクチュエータ,森北出版,1986
3)一ノ瀬昇,圧電セラミックス新技術,オーム社,1991
4)T.Yamamoto and F.Mizuno:Jpn.J.Appl.Phys.34,2627-31,1995