 香気性味噌酵母の開発
香気性味噌酵母の開発
- 目的
近年、嗜好の多様化、高級化が進む中で、伝統的な食品である味噌、醤油などの醸造分野においても、風味に優れた製品の開発が望まれている。とりわけ、香りの生成に重要な役割を果たす耐塩性酵母の香気生成能を高めることは重要な課題の一つである。
本研究では、これまでに、味噌の風味を高める香気成分として重要視されているイソアミルアルコ−ルを、液体発酵で元の酵母の2倍以上生成する芳香性に優れた耐塩性酵母を育種・分離した。そこで、この新規酵母を用いて味噌の試醸を行い、酵母添加による味噌の香気向上に及ぼす効果について検討を行うことを目的とした。
- 内容(実験方法)
2.1 供試菌株
県内の味噌・醤油製造企業で使用されている主発酵耐塩性酵母 Z.rouxii D株 [ DY(P) ] と、これをもとに育種した5、5、5−トリフルオロ−D、L−ロイシンに耐性な株で、イソアミルアルコールを DY(P) の2倍以上生成する芳香性に優れた新規株 [ D-5D-4 ] を用いた。
2.2 原料処理及び配合割合
丸大豆は15時間浸漬後約20分水切りし、0.3kg/cm2で15分蒸熟した。蒸熟した大豆は直径2mmの目皿をもつミンチで磨砕した。製麹は内地精白米で常法により行った。仕込み配合は、表1に従って行った。重石は1.0kgに統一した。
表1 仕込み配合
| 蒸煮大豆 | 2500g |
| 米 麹 | 2500g |
| 食 塩 | 2500g |
| 種水(酵母培養液を含む) | 421g |
計 5004g |
2.3 仕込み区及び熟成条件
酵母無添加区と従来酵母 [ DY(P) ] を添加した区を対照とし、新規酵母 [ D-5D-4株 ] 添加区を試験区とした。熟成条件は、30℃で54日間温醸し、その後15℃で90日目まで熟成した。途中、18日目に切り返しを行った。酵母の添加量は、味噌1gにつき2×105にて行った。
2.4 香気成分分析
味噌の香気成分の分析は、味噌3gに飽和食塩水4mlを加え、50℃で30分間保温後のヘッドスペ−スガスをキャピラリ−カラムによるガスクロマトグラフ法により行った。
2.5 官能審査
パネラー40名により、熟成終了後の味噌の色、味、香り、総合評価の各項目について、順位法(良いものから1、2、3の順)による官能審査を行った。
- 結果
3.1 味噌の分析
90日熟成後の各味噌の水分、食塩、pHの分析結果を、仕込み直後の値(括弧内の数値)とともに表2に示す。いずれも仕込み直後に比較して、水分の減少と塩分濃度の増加がみられたが、ほぼ同程度の値であった。また、酵母添加区の生酵母数は、いずれも25日目に4.3×106/gの最高菌数に達し、良好な増殖を示した。
表2 味噌の分析結果
(熟成日数:90日、( ) 内は仕込み直後の分析値)
| 区 | 測定項目 |
| 水分(%) | 食塩(%) | pH |
| 酵母無添加区 | 41.1(45.5) | 13.3(12.6) | 5.00(5.98) |
| DY(P)添加区 | 42.3(45.4) | 13.3(12.7) | 4.95(5.98) |
| D-5D-4添加区 | 42.0(45.6) | 13.3(12.8) | 5.03(6.00) |
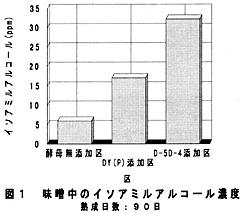 3.2 香気成分
3.2 香気成分
味噌の香気成分のうち、味噌の風味を高める高級アルコールの一つ、イソアミルアルコ−ル含有量の分析結果を図1に示す。その結果、D-5D-4株添加の味噌は酵母無添加味噌の約5.4倍、DY(P)株添加味噌の約1.9倍高い値を示し、新規酵母が液体発酵のみならず、味噌中においても高いイソアミルアルコール生成能を発揮することを示した。さらに、液体発酵では生成されず、味噌のような半嫌気的条件下でのみ特異的に生成するとされるn−ブタノールについても、新規酵母添加区では従来酵母添加区の約1.8倍高い含有量を示し、新規酵母添加による味噌の香気向上に効果が認められた。
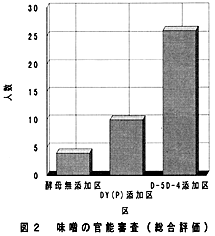 3.2 官能審査
3.2 官能審査
味噌の官能審査のうち、総合評価について行った結果を図2に示す。色、味、香りの総合評価で、40名中26名が新規酵母添加の味噌に最良点を与え、従来酵母添加の味噌の10名、酵母無添加味噌の4名を大きく上回った。その結果、新規酵母添加による味噌の香気成分量の増加が、官能的にも裏付けられた。
‖前のページへ戻る‖
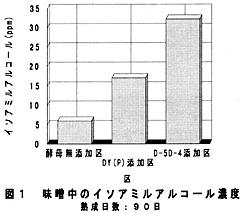 3.2 香気成分
3.2 香気成分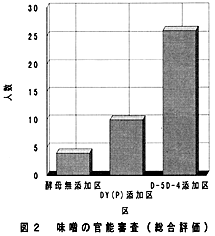 3.2 官能審査
3.2 官能審査