 漆器椀の変色防止技術
漆器椀の変色防止技術
製品科学部
情報指導部
|
市川太刀雄・江頭 俊郎
坂本誠
|
|
- 目的
漆器製品の椀、盆、座卓等は、温熱水に触れると塗膜表面が黒色から褐色に変色する欠点が以前から指摘されていたが、多くの人は、これまで合成樹脂塗料を塗布した什器に慣れ、器の中に沸騰直後の汁を入れたり、食器洗浄器による温熱水中に長時間さらしたりしている。このように漆塗り製品の取り扱い方を忘れてしまったことが、漆塗膜の変色をより早める結果となっている。この変色の原因は、漆塗膜中の水可溶成分であるゴム質が温熱水に溶出1)することに起因していることが分かっている。しかし、その対策は、未だ見つかっていない。このため、本研究では、適正な製漆方法(なやし:攪拌、油脂添加量)やカーボンブラック、ウルシオール添加等の改良を加え、変色の少ない黒漆の製漆技術の確立し、椀による実用試験を行うことによって、業界へのスムーズな技術移転を図ることを目的とた。
- 内容
2.1 実験項目
(1)漆塗膜の鉄含有量と熱水による変色
(2)製漆時のなやし時間と熱水による変色
(3)つや剤の添加量と熱水による変色
(4)カーボンブラックの添加量と熱水による変色
(5)改質漆(ウルシオール添加、分散乳化処理)の熱水による変色の関係
(6)椀の繰り返し熱水試験及び実用試験と変色の関係
2.2 供試材
(1)使用漆
生漆:中華人民共和国1990年安康産A、1990年安康産B、1994年城口産を使用した
透つや漆:市販品
ウルシオール:市販品(中華人民共和国から輸入)
(2)つや剤
荏の油、チャン(チャン:松脂と荏の油を加熱溶融した粘性物質)
(3)着色剤(黒色)
鉄黒: 硫酸第一鉄水溶液にアンモニア水(25 sol%)を添加し、水酸化第一鉄の沈殿物を作り、濾紙により濾過した沈殿物(鉄換算による添加量:0.14、0.21、0.32、0.68、0.98wt%、0.4部)を使用した
カーボンブラック:市販品11種類の中から変色防止に効果のある1種類を選定(1〜8wt%、3部)添加した
2.3 製漆
(1)使用製漆機
桶の寸法:径20×高さ10cm、羽根角度:90度、羽根枚数:2枚、羽根の回転数:60rpm、 加熱熱源:赤外線ランプ(0.22W/平方cm)
(2)製漆条件
表1に製漆方法を示す。
1)常法製漆
製漆機に200gの生漆と鉄黒、つや剤を加え、なやし(攪拌)、くろめ(攪拌、水分除去)工程を行い精製漆を作った。
2)分散乳化処理製漆
なやし工程の代わりに高速分散乳化機(イストラル社製:フローユニットZ48型)で、生漆を1〜2回通過(分散乳化処理)させた後、製漆機で精製した。
3)カーボンブラック添加による製漆
カーボンブラックに4〜5倍のメチルアルコールを加えペースト状にした後、生漆100部に3部加え製漆した。また、ウルシオールにカーボンブラック(25wt%)を加え、3本ロールミルで混練した着色剤を透つや漆(市販品)に1〜8wt%添加し、黒漆を作った。
表1 各精製漆の処理条件、物性
(注:25×103 は 25×103 以上を表す)
試片
NO. |
漆産地
採取年度 |
項 目 |
| 製漆時の配合割合(部)、(wt%) |
製漆方法 |
生漆
(部) |
油脂
(部) |
鉄に換算
(約) |
ウシオール
(wt%) |
カーボン
ブラック |
ナヤシ
時間・秒 |
分散
乳化処理 |
| 1 |
安康A1990年 |
100 | 20 | 0.1〜1wt% | − | − | 60 | − |
| 2 |
市販 透ツヤ漆 |
− | − | − | − | 1〜8wt% | − | − |
| 3 |
城口 1994年 |
100 | 5 | 0.4 部 | − | − | 0 | − |
| 4 |
城口 1994年 |
100 | 5 | 0.4 部 | − | − | 15 | − |
| 5 |
城口 1994年 |
100 | 5 | 0.4 部 | − | − | 30 | − |
| 6 |
城口 1994年 |
100 | 5 | 0.4 部 | − | − | 60 | − |
| 7 |
城口 1994年 |
100 | 0 | 0.4 部 | − | − | 40 | − |
| 8 |
城口 1994年 |
100 | 5 | 0.4 部 | − | − | 40 | − |
| 9 |
城口 1994年 |
100 | 10 | 0.4 部 | − | − | 40 | − |
| 10 |
城口 1994年 |
100 | 15 | 0.4 部 | − | − | 40 | − |
| 11 |
城口 1994年 |
100 | 20 | 0.4 部 | − | − | 40 | − |
| 12 |
安康B1990年 |
100 | 5 | 0.4 部 | − | 0 部 | 40 | − |
| 13 |
安康B1990年 |
100 | 5 | 0.4 部 | − | 3 部 | 40 | − |
| 14 |
安康B1990年 |
100 | 20 | 0.4 部 | − | 0 部 | 40 | − |
| 15 |
安康B1990年 |
100 | 20 | 0.4 部 | − | 3 部 | 40 | − |
| 16 |
安康B1990年 |
70 | 5 | 0.4 部 | 30 | 0 部 | 40 | − |
| 17 |
安康B1990年 |
70 | 5 | 0.4 部 | 30 | 3 部 | 40 | − |
| 18 |
安康B1990年 |
100 | 5 | 0.4 部 | - | 0 部 | 0 | 1 回 |
| 19 |
安康B1990年 |
100 | 5 | 0.4 部 | - | 3 部 | 0 | 1 回 |
2.4 塗膜作製方法
ガラス板(L405×W77×t2mm)、フェノール樹脂積層板(100×100×t8mm)、木材(ミズメザクラ)椀(φ125×H70mm)に精製漆をフイルム・アプリケータと漆刷毛を使って塗布し、自動漆乾燥風呂を使い、[ 20℃・60%RH・4時間 ] >>> [ 20℃・70%RH・18時間 ] >>> [ 20℃・80%RH(乾燥の遅い漆は25℃・85%RH)・24〜48時間 ] 乾燥した後、約1〜3カ月間自然乾燥した試験片を実験に用いた。なお、椀の一部は、漆器製造業者に塗装を依頼したので、乾燥条件は不明である。
2.5 変色促進試験方法
1)促進熱水試験
促進熱水試験機(田中科学機械製特注)に漆塗りフェノール樹脂積層板を熱水面(φ60mm)に当て、温度86〜90℃で熱水試験を行った。
2)お椀の繰り返し熱水試験
1サイクルの試験条件:
沸騰水 >>> 5分間放置(75℃) >>> 25分間放置(温水) >>> 排水 >>> ガーゼで水を拭き取る >>> 90分放置
3)椀実用化試験
椀を一般家庭で実際に什器として使用した。
2.6 塗膜の物性測定
1)光沢度測定:光沢計
2)色味、色差測定:スペクトロ・カラーメータ

- 結果
3.1 漆塗膜の鉄含有量の違いと熱水による変色
図1に鉄含有量と促進熱水試験による色差の変化を示す。鉄の添加量に関係なく、熱水処理時間の経過と共に色差は直線的に増加した。鉄の量が多くなると変色は少ないが、高粘度になり刷毛塗りが不可能となる。
従って、鉄の添加量は0.3〜0.4wt%の量が適量であった。
3.2 なやし(攪拌)時間の違いと熱水による変色
なやし時間60分の塗膜は、初期の変色防止効果は期待できるが、長期間の場合は、他の塗膜より色差が大きいことが分かった。
図2になやし時間の違いによる促進熱水試験後の塗膜の色味変化を示す。熱水試験の時間経過とともに、黒から赤褐色や黄褐色に変化した。なやし時間0分の塗膜は、赤褐色で無色(鈍い色)に近く、なやし時間60分の塗膜は、鮮やかな黄褐色に変色した。その原因は、ゴム質がなやしにより微細化したため、熱水で溶出したゴム質の空洞が光の拡散反射をより大きくしたと考えられる。
3.3 つや剤の添加量の違いと熱水による変色
図3につや剤の添加量の違いと促進熱水試験による色差変化を示す。
つや剤を10、15、20部添加した塗膜は、初期の変色を防止する効果があった。
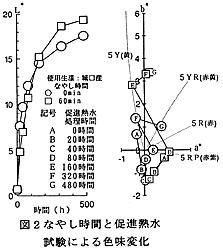
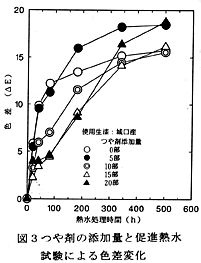
3.4 カーボンブラックの添加量と熱水試験による変色
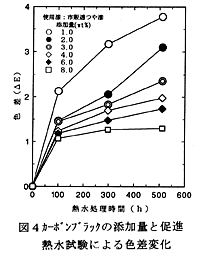 図4にカーボンブラック添加量と促進熱水試験による色差の変化を示す。カーボンブラック添加による隠蔽効果を利用することで、熱水による変色を抑える効果があった。また、カーボンブラックの添加量は、漆100部に3〜4部が良好であった。
図4にカーボンブラック添加量と促進熱水試験による色差の変化を示す。カーボンブラック添加による隠蔽効果を利用することで、熱水による変色を抑える効果があった。また、カーボンブラックの添加量は、漆100部に3〜4部が良好であった。
3.5 改質漆(ウルシオール添加、分散乳化処理)の変色
ウルシオールを添加した塗膜は、変色防止に効果があることが分かった。
3.6 椀の繰り返し熱水試験及び実用試験
ウルシオールを添加した塗膜は、300回で色差3.2と変化が小さく、変色防止効果が大きいことが分かった。しかし、常法製漆や分散乳化処理の塗膜は、初期の段階で変色した。
色相の変化は、試験前は青紫かかった黒色であるが、繰り返し熱水試験を行うと赤褐色や黄褐色に変化した。特に、つや剤20部添加塗膜の色相は、黄褐色に変化し視覚的に変色が大きかった。ウルシオール添加塗膜は、鈍い赤褐色で色相の変化は小さい。従って、促進熱水
試験での結果と同様に椀による試験でも変色の防止効果が実証された。
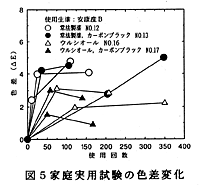 図5に椀の家庭実用試験の色差の変化を示す。
図5に椀の家庭実用試験の色差の変化を示す。
椀の一般家庭での実用試験は、繰り返し熱水試験より試験条件が緩やかである。また、試験条件(使用回数、汁の温度、洗浄方法等)が一定ではないので、数値の比較は難しい面があった。しかし、得られた数値や視覚的ものから判断をすると、カーボンブラックやウルシオールを添加する方法が最も変色の防止に効果があった。
参考文献
坂本誠、市川太刀雄、江頭俊郎:
黒漆の変色防止に関する研究、石川県工業試験場研究報告,41
p.23-31(1993)
‖前のページへ戻る‖

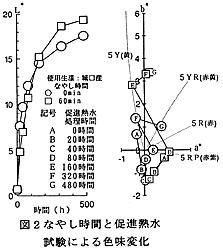
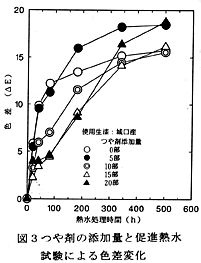
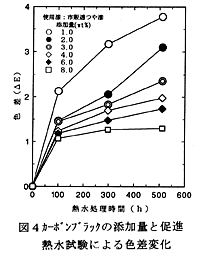 図4にカーボンブラック添加量と促進熱水試験による色差の変化を示す。カーボンブラック添加による隠蔽効果を利用することで、熱水による変色を抑える効果があった。また、カーボンブラックの添加量は、漆100部に3〜4部が良好であった。
図4にカーボンブラック添加量と促進熱水試験による色差の変化を示す。カーボンブラック添加による隠蔽効果を利用することで、熱水による変色を抑える効果があった。また、カーボンブラックの添加量は、漆100部に3〜4部が良好であった。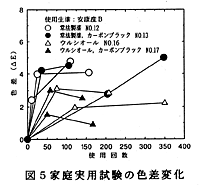 図5に椀の家庭実用試験の色差の変化を示す。
図5に椀の家庭実用試験の色差の変化を示す。