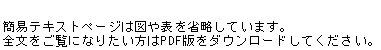
| 全文 (PDFファイル:135KB、1ページ) |
| 視覚障害者用色識別装置「カラートーク」の開発
|
||
| ■ 株式会社北計工業 福祉機器部 一二三吉勝 |
■技術開発の背景
石川県バリアフリー機器等開発研究調査会の活動の中で,視覚障害の方々から「日常生活の中で,色を識別できないことによって不便なことが多い。」という意見を聞いた。さらに調査を進め,視覚障害者にとって「何時でも,何処でも色を知ることのできる色識別装置」の開発が切望されていることが分かった。
図1 色識別装置の原理
■技術開発の内容
測色したい物体に光をあて,その散乱反射光のRGB(Red:赤,Green:緑,Blue:青)成分を測定し,その測定値に対応した色を言葉で表現する技術を開発した(図1)。
図2 色表現方法
■製品の特徴
本装置の主な特徴を以下に示す。
(1)測色結果の安定化
携帯することで,測定環境が変化し,測色結果が不安定となる。そこで,独自の自己校正機能により測色結果を安定させた。
(2)言葉による色の表現
図3 装置外観
測色結果は数値でしか得ることができず,一般的に人間が色を想像することは難しい。そこで基本色名に修飾語を組み合わせた言葉による色表現方法を開発した。さらに,モニタ調査の結果,使用場面により希望する識別方法が異なることが分かり,図2に示すような31色の簡易モードと220色の詳細モードの色表現方法を設け,場面に応じて使い分けを可能とした。
■今後の展開
開発した色識別装置(図3)は「カラートーク」という商品名で,2001年4月1日より国内発売を開始した。今秋よりヨーロッパでの発売を開始する予定である。また,障害者が入手しやすくなるような認定申請を継続して実施していく。