
いしかわ工試
技術ニュース 1995 9.1 Vol.20 No.2
セラミックス燃料電池の特性向上
化学食品部 北 川 賀 津一
1.概要
燃料電池は排ガス、騒音、振動等の環境への影響が少ないので、次世代の発電システムとして期待されています。その中でも安定化ジルコニアを材料に使用した固体電解質型燃料電池は、高い発電効率が得られるので、離島や都市等の分散型電源として、幾つかの研究所で開発が進められています。
しかし、電極の空気極側では、電気特性の低下が大きいため、実用化のネックとなっています。
本研究では、空気極に使用する材料の化学組織を変えることにより、その電気特性の低下防止と材料物性の向上を図りました。
|
2.内容 一般に固体電解質型燃料電池(図1)の開発では、空気極の材料として、ランタンマンガナイト(La11-XSrXMnO3)を用いています。本研究では、新たに金属酢酸塩から合成したランタンマンガナイトを用いました。 3.結果 (1)ランタンマンガナイト粒子の製造 通常はランタン(La)とマンガン(Mn)を混合する方法で合成されています。本研究では、酢酸塩からの結晶法(ゾルーゲル法)で実験したところ、ランタンマンガナイトの微細な粒子が合成でき、結晶構造が安定しました。 (2)発電特性の評価 ランタンマンガナイトのストロンチウム(Sr)含有量を変えて、電気特性を調べました(図2)。Sr含有量が増加すると発電特性が向上し、モル比X=0.3で最大効率を示しました。 これはLaをSrに置き換えることにより、ランタンマンガナイトの結晶構造の中にできた酸素空孔によって酸素が活性化され、発電特性が向上したものと考えられます。 工業試験場では、エネルギー利用技術研究会等を通じて、燃料電池を含めた「新エネルギー」の有効利用を図っていく予定です。 |
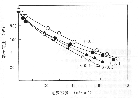 図1 個体電解質型燃料電池の 発電原理 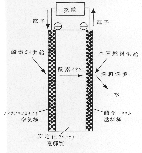 図2 開発した燃料電池用 材料の電気特性 |
産業廃棄物への対応すすむ
-鋳物工場における粉塵の減量化に挑戦-
 鋳造工場の砂処理状況を調査 |
鋳造工場では、作業中に発生する粉塵を集塵機で吸引し、作業環境の保全に勉めています。しかし、吸引力が必要以上に強いと、未使用の高価な原料まで吸い込んで、廃棄処理してしまうことになります。この原料の無駄や廃棄物処理に要する費用と労力は県内企業の大きな負担になっています。 産学官による「鋳造工場の環境保全研究会」の参加企業2社と連携し、集塵装置や集塵方法を検討し、廃棄物が少なくなるよう実験を続けています。 (機械電子部) |
糸くずから燃料ができる
-繊維廃棄物の固形チップ化に成功-
|
織布工場では、捨て耳と呼ばれるくず糸や原糸を巻いてある紙管等大量の繊維廃棄物の処理に困っています。 これに対処するため、(社)県繊維構造改善組合、(株)日本リサイクルマネジメントと共同で繊維廃棄物固形化装置を開発しました。 この装置は、くず糸や紙管を粉砕・混合して円筒状のチップにすることができます。このチップは、固形燃料として利用できることを確認しました。 今後は、建築資材に応用するための試験を行っていきます。 (繊 維 部) |
 繊維廃棄物とチップ状の固形燃料 |
プラスチックもリサイクル
-FRP廃棄物からガラス繊維を分離する技術を開発-
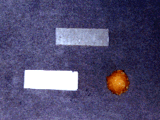 劣化前のFRPと劣化した FRPおよび分解生成物 |
ガラス繊維で強化したプラスチック(FRP)は耐久性が良いために、製品寿命が尽きた後の処理や再利用が問題となっています。 今回、このFRP廃棄物の処理に、アルカリや熱水を利用してFRPの劣化を促進させ、強化材であるガラス繊維の分離(写真左下)や樹脂の分解物の回収(写真右下)に成功しました。 現在、効率的な劣化促進方法や回収したガラス繊維、分解物の再利用方法の検討を進めています。 (製品科学部) |
石炭灰が都市景観タイルに変身
-火力発電所の廃棄物を有効利用-
|
石川県内で石炭火力発電所が稼働をはじめたことから、石炭灰の大量排出が予想されます。 そこで、この石炭灰を断熱れんがや建材、タイル等の窯業原料として有効利用するための研究を進めています。 今回、電子用のセラミックス製造技術を応用して、景観用タイルを試作しました。 (化学食品部) |
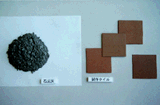 石炭灰を材料に試作した 景観用タイル |
技術交流の輪広がる
-ほっと技術ふれあい’95を開催-
  研究・指導成果物の展示 |
7月4日〜6日に、日頃の業務内容を県民に知ってもらい、交流を深めるために、「ほっと技術ふれあい’95」を開催しました。 期間中には、技術アドバイザーによるPL法やISO9000規格の相談会、特許出願・検索の相談会、研究・試験施設や成果物を展示した研究室めぐりを開催しました。さらに、基調講演と18テーマの研究・指導成果発表会を行いました。 今回は、初めての試みでしたが、大勢の参加があり、今後の技術交流の輪が広まるものと期待しています。 (情報指導部) |
佐渡室長 優良研究指導業績で表彰
|
平成7年6月28日佐渡康夫食品加工技術研究室長が、全国食品関係試験研究場所長会長賞を受賞しました。 受賞は、能登地方につたえられている魚醤(いしる)をはじめとする食品関連の研究、および技術指導の功績が認められたものです。 魚醤の研究では、初めて化学的に成分分析を行い、「うまみ」の成分を解明しました。 |
 佐渡 食品加工技術研究室長 |